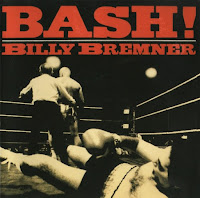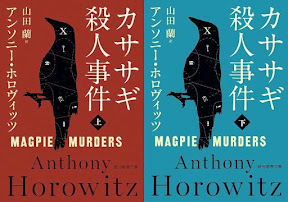2019-12-27
法月綸太郎「赤い部屋異聞」
過去の名作をベースにした、というくくりの9作品が収められた短編集。はっきりと原典がわかるオマージュからモチーフのひとつとして取り入れている程度のものまで、スタンスはさまざま。バラエティに富んだ内容で、ミステリ作家としてのショウケースのような趣もありますか。
タイトルからしてすぐにそれ、とわかるのが「赤い部屋異聞」と「続・夢判断」。
「赤い~」の設定はもちろん大乱歩の有名作だが、そこから捻って捻ってという展開や、あえてすっきり落とさない結末は新本格というか幻影城というか。表題作だけあって、非常に力のこもった出来。
「続・夢判断」の方もいかにも新本格らしいよなあという、弄り回した一作なのだが、このような「奇妙な味」風の作品に形の整った絵解きを入れるというのも、わかるのだけれど、原典のことを考えるとスマートさに欠けるという気も。いずれにせよ、この作家らしい。
ミステリらしいミステリ、「砂時計の伝言」はパズルとしてはあまりにシンプル過ぎるのですが、ダイイングメッセージの取り扱いが現代的といえましょうか。被害者による倒叙形式と捉えればすっきりはまるのだけれど。変なことを考えるものだと思うし、それを作品として完成してしまえるというのも大したものだ。
なんだか趣味に走ってるなあ、というのが「対位法」。物語の終盤に来て、ようやく元となる作品の当たりがついた。結末はリドル・ストーリーのかたちをとっているが、強引に解釈すれば確定はできる(もっとも、そうする意味はないが)。
『挑戦者たち』にも収録されていた「最後の一撃」は独立した短編として充分成立しているし、むしろ単独で読んだほうがオチの意外性を感じられていいかも。
その他ではホラーにいいものがあったのが収穫。「葬式がえり」での予想のつかないところへの落とし方はミステリ作家ならでは。アイディアのいただきがひとつの作品からではない、というのもミソか。「だまし舟」は割合とオーソドックスな展開ですが、架空の作り込みには力が入っていて、本格的なものになっている。
小味な芸が楽しめる、書いていて楽しかったのではないか、という気がする一冊でした(前にもこんなこと書いていたな、いいのか?)。
2019-11-24
James Brown / Live At Home With His Bad Self
1969年10月1日、ジェイムズ・ブラウンは故郷ジョージアのオーガスタにあるベル・オーディトリアムでホームカミング・コンサートを行った。そのライヴは「James Brown At Home With His Bad Self」というタイトルでのアルバム化を意図したものであった。しかし、数ヵ月後になってバンドのメンバーが大量離脱することによって、その企画は立ち消えとなる。
翌年の春、新しいバンドによるシングル "Sex Machine" がヒットしたことを受けて、同タイトルのダブル・アルバムが制作された。一枚目はスタジオライヴに観客の歓声をオーバーダブした疑似ライヴである。深いエコーが気持ち悪く、個人的には好きではないサウンドだ。そして、その二枚目には(二曲を除いて)お蔵入りになっていた前年のホームカミング・コンサートの音源が使用された。こちらも編集は乱暴で、いかにもJBらしい。
 |
「Sex Machine」カバー裏より "LIVE AT HOME IN AUGUSTA, GEORGIA WITH HIS BAD SELF" |
前置きが長くなったが、このライヴ・アルバムは「Sex Machine」アナログ二枚目に収録されていたものの拡大盤となる。七曲が未発表となるもので、残りも新たにミックスされており、曲によっては明らかにピッチが変わっています(従来のものは遅かったらしい)。
音質のほうは時代を考えればまあ上々か、序盤はややレンジが狭いかな、という感じ。しかし、当然のことながら演奏は最高オブ最高。なんたって1969年のジェイムズ・ブラウン・オーケストラなのだ。こんなこと毎日続けていたらそのうち死ぬぞ、という緊張感。
オープニングの "Say It Loud - I'm Black And I'm Proud" は編集盤「Motherlode」にも収録されていたが、そちらはDJ仕様なのかライヴのアンビエンスを取り除くようなミックスがされていて変な感じがしたものだ。今回は客の反応もばっちり、盛り上がる。
また、"There Was A Time" の尺がかなり伸びているのも嬉しいところ。ここから未発表であった "Give It Up Or Turnit A Loose" へとなだれ込む流れはこの盤のハイライトのひとつだ。
あと、"Mother Popcorn" も「Sex Machine」のと比べると相当に長くなっているのだが、これは編集盤「Foundation Of Funk」にも入っていたな。
個人的にはこの時期のJBがベストだと思っている。メンバーの充実に加えて、シンガーとしての状態もあって。"It's A Man's Man's Man's World" の歌い出しなど、ぐっときます。
2019-11-10
The Beatles / Abbey Road
「Abbey Road」のリミックスを聴いて考えたのは、なんでこんなものをわざわざ作ったのだろう、ということだ。全体としては大して印象の変わらないものを作る、その意図がわからない。音質が劇的に向上しているとも思わない。これならオリジナルを聴けばいいじゃない。
しかし、そもそもリミックスというのは昔の素材ほど扱いが難しい。ビートルズの音楽に新たなセンスを付け加えたものなんて聴きたいか? しかも実際のレコーディングに関わったやつらはいないんだぜ? どうしたって勝ち目は無い。
そうすると、制作者の意向はむしろ、未発表テイクの仕上がりにこそ反映されているのではないか。ドライなエコー、ソリッドなギターは実に格好いい。本編よりもバンドらしいダイナミズムを感じる。この調子でアルバムもミックスできればよかったのだろうが。
| ブックレットの最初のページ、とてもダサい。それはそうと、なんで「THE」をつけたのだ? |
よくアルバム「Sgt. Pepper~」について、楽曲の出来自体がいまいち、という意見を見るのだが、個人的には「Abbey Road」のほうが落ちるじゃん、と思っている(勿論ビートルズとして、という高いレベルでの話ではあるけど)。しかし、サウンドのつくりやアレンジ、構成での聴かせかたがとんでもなく素晴らしい。それが後進のUKモダーンポップに与えた影響がなんて始めると、またしゃらくさい話になってしまいそうだ。
"Oh that magic feeling, nowhere to go"、つまりはそういうことなのね。このくだりにくるといつも、うんうん、その感覚なんだよ、となる。まったくうまくは説明できないけれど、夢の中かもしくは海底みたいなね。
2019-10-14
フィリップ・K・ディック「フロリクス8から来た友人」
22世紀、世界は脳の突然変異で高い知性を持つ〈新人〉と超能力者である〈異人〉が支配、エリートである彼らと残りの人類〈旧人〉の間にはっきりした階級社会が形成されていた。その〈旧人〉たちの救世主たる男、トース・プロヴォーニは〈旧人〉たちが暮らすための新惑星を見つけるべく単身、深宇宙への探索へと出て行ったきりであった。
1970年長編。
勢いに乗っていた時代の作品だけあって、序盤で物語にすぐ引き込まれるし、設定もすごく面白そうではある。また、ディック作品ではおなじみ、まやかしの現実というモチーフがここでは中心に置かれていないため、とても読みやすい。
しかし、ディストピアとそこからの解放というシンプルなテーマ、ご都合主義的な展開も明らかにそこに沿っているように見えたのだが、個々人の欲望と情動によって、いつしか物語は勝手な方向に向かっていく。そしてディック作品ではよくあることではあるけど、色んな問題は未解決なまま、みせかけの奇妙な平安に帰着する。
物語前半に出てきた重要そうな人々やアイディアが後半には登場しなくなるし、キャラクターの一貫性にも乏しい。なおかつ、印象的な場面は多いのだ。ちゃんとしたプロットを立てずに思いつきで話をつないでいったようである。間違いなくファン向け。
そしてファンなら最終章での会話を読んで、この作品を受け入れてしまう。困ったものだ。
2019-10-05
有栖川有栖「カナダ金貨の謎」
作家アリスもの新刊は中編3作の間に短編ふたつが挟まれた構成の作品集で、タイトルは国名シリーズだが中身はフルハウス、とのこと。
「船長が死んだ夜」 容疑者が限定された状況でのフーダニットは、ある手掛かりに関するホワイ?を軸にしたもの。これがちょっとした飛躍が要求されるもので、気付けそうで気付けない。
謎解きそのものは手堅いもので、まあまあの出来かなと思っていたところに、幕切れに待ち構えていた伏線回収にやられた。事件の様相をがらっ、と変える類のものではないが、実に形がいい驚きであります。
「エア・キャット」 犯罪は起こっているけれど、そこは話の中心ではないです。謎と解決は備えていますが、その解かれ方はミステリでもないような。
「カナダ金貨の謎」 事件そのものはいたって地味なもの。しかも倒叙形式なので犯人はわかっているのだが、犯行計画そのものは語られないので、そこに謎が発生する。それにしてもこのホワイ? は絶妙な設定で、解き明かされた瞬間、ああ!判ってもよかったのに、となりました。そして、そこから一息に全容が展開されていく鮮やかさよ。
また、事件に物語を見出すことによりミステリとしての奥行きを生みだす、という作家アリスの役割からは、そのバランスの良さにいつも感心させられます。
「あるトリックの蹉跌」 物語の枠組みは完全にフォー・ファンズ・オンリー、なのだが、作中で解説されているトリックは懐かしの新本格風でちょっと面白い。もったいない使い方だなと思ったのだが、このひとの作風だとうまく生きないのかもしれない。
「トロッコの行方」 アリバイもののようで実は、というフーダニットは意外な真相と、それを生かした切れのある結末がなかなか。一方で、手掛かりは不十分ではないか、何か見落としていたか。いや、ウイッグの件からすると、読者をひっかける方に力が入れられていたのかも知れないけれど。
いつもながらうまいし、テクノロジーやトピカルなテーマの取り込みにも違和感がない。
そして、謎解き小説において犯人側のロジック、というのは下手をすると取ってつけたようになりかねないのだろうが、際を攻めつつ、その境界をじわじわと拡げているようでもあります。
2019-09-17
法月綸太郎「法月綸太郎の消息」
随分久し振りになる探偵法月ものは中短編4作品を収録した作品集。
「白面のたてがみ」
ホームズ譚中、「白面の兵士」と「ライオンのたてがみ」は何故名探偵の一人称で語られたのか。出来がいまいちな二作品を俎上に載せたディスカッションが展開される一編。
チェスタトンのガブリエル・ゲイル短編についての気付きから始まる推理はおそろしくスリリング。なおかつ、その推理を一旦ペンディングするバランス感覚も素晴らしい。
一方で、ドイルやチェスタトンに大して関心のない読者はどう感じるだろうか。いずれにせよマニア向けであるのは確か。
振り返ってみれば作品の書き出し部分の文体には、なるほどそういうことか、と思わされる。
「あべこべの遺書」
ふたつの遺体、ふたつの遺書、だがその遺書が入れ替わっていたら?
『退職刑事』の形式(立場は逆だが)を使って語られる事件は、その設定もいかにも都筑道夫を思わせる不可解なもの。法月警視が(先入観を与えないという建前で)情報を小出しにしていくことで、推理のスクラップ&ビルドも可能になっている。推理の飛躍が起こるときの根拠がやや乏しいところも本家『退職~』並みではあるけれど、細かい証拠の符合は気持ちいい。
「殺さぬ先の自首」
これも安楽椅子探偵もので、『退職刑事』シリーズを思わせるような(というか、あとがきによればまさにそこから取ってきたそうだ)道理に合わない謎。
見かけはフーダニットだが、事件の構造、というか何が核心なのかは普通に考えていてもわからない。要は奇妙な論理ものなので、その程度によってはパズラーの範囲から少しはみ出ているかもしれない。
はたして作品の主眼はどこにあるのだろう。
「カーテンコール」
100ページちょっとと、本書では一番分量がある作品なのだが、クリスティのある作品について新たな仮説を打ち出し、それを検証していくという内容。ほぼ全編にわたりディスカッションが繰り広げられ、小説の形式をとったクリスティ論、といったおもむき。
いくつかの作品の結末に言及されているし、クリスティに親しんでいないと全く意味不明かもしれない。わたしはこのブログにクリスティのミステリ作品はおおかたあげていたのだが、そんなに細部まで覚えているわけではない。
しかし、ここで主張される説、そしてロジックは目茶滅茶面白い。
この作者らしさは堪能しましたが、「カーテンコール」以外はちょっと小粒かもね。
なお、帯によると12月に角川から『赤い部屋異聞』というタイトルの作品集が出るそうで、こちらも楽しみ。
2019-09-01
The Sergio Mendes Trio Introducing Wanda De Sah With Rosinha De Valenca / Brasil '65
このところ、こればかり聴いていた。何が悲しゅうてセルメンを、と思わなくもない。凄く良く出来ているけれど、情緒に深く訴えられることはない、そこがいい。クールです。
セルジオ・メンデス率いるピアノ・トリオがシンガーとしてワンダ・サー、ギタリストにホジーナ・ジ・ヴァレンサ、フルートorサックスにバド・シャンクを迎えた1965年盤、キャピトルからのリリース。
取り上げられているのはブラジル産の有名曲ばかりですが、まあ、品がいいね。サックスが入った曲では、その瞬間に空気が変わってしまう、そう感じるくらい。
セルジオ・メンデス・トリオは全体の半数を占めるボーカル入りの曲においては歌伴と化して、でしゃばらない。冒頭の "So Nice" なんてまさにそう。また、"Berimbau" ではバックコーラスが欲しくなるほどだ。プロデューサーの意向があったのかもしれんけどね、アルバム・カバーでの写真の扱いもそういうことだし。
インストでも "Tristeza Em Mim" を聴くと主役はギターなのだが、ともかくセルメンたちの個性は歌なしの曲において発揮されているとは思う。特に、トリオ演奏による "Favela" ね。深い音色のベースのリフがかっちょよく、カラフルなピアノのフレーズも一層映える。それにしてもやり過ぎない、バランスを取った音楽ではあります。
後のブラジル'66と比較するとジャズですね、やっぱり。いや、どっちもいいのだけれど。
しかし、最後の "Reza" に関してはピアノ抜きで聴いてみたい。もはや歌とギターだけで充分成立してしまっているのではないか。
2019-08-18
The Spinners / While The City Sleeps
英Kentは近年、モータウンの古いカタログからの発掘にも力を入れていますが、そんなKentより昨年に出されたのがこれ。副題は「Their Second Motown Album With Bonus Tracks」ということで、スピナーズのアルバム「2nd Time Around」にボーナストラックとして当時は未発表だった曲が13曲収録されています。
"It's A Shame" を聴くたびにいつも気になっていたのがイントロのギターのよれというかノイズ。Kentならひょっとして、と思っていたのですが、やっぱりありました、残念。しかし、それを除けば例によって良好なマスタリングであります。
「2nd Time Around」は1970年、"It's A Shame" の大ヒットを受けて急遽制作されたアルバムで、その内訳はシングルで出ていた曲に加えて、録音されていながらそれまでリリースされてこなかったものが4曲、そしてアルバム用に新たにレコーディングされたヒット曲カバーが3曲。録音時期には1967年から'70年とやや幅があります。
この時期のスピナーズというと、やはりG.C.キャメロンの豪快なリードが聴き物。特に、強目にミックスされたリズムに対して真っ向から渡り合う "Souly Ghost"、一転して甘いバックに荒々しい歌唱のコントラストが映えるファイヴ・ステアステップスの "O-o-h Child" と続くところが格好良い。
また、ボーカルグループとしての聴かせどころもあって、それがアルバムに幅を持たせているのですが、曲によってはもろテンプテーションズ・スタイルのコール&レスポンスも繰り出されます。ライナーを読むと実際、いくつかの曲はもともとテンプスにあてがわれたものであったそうで、スピナーズはモータウンでは二番手以下の存在だったのだな、と再認識したり。
ボーナストラックは13曲中配信オンリーで出たものが3曲、残りは完全未発表ということになります。もっともスピナーズはモータウン在籍時に130曲を録音した、ということなのですね。この盤に収録されたものに関しては完全に仕上げられたものばかりで、出来もそこそこのレベルはクリアしているとあって、流石は往時のモータウンという感じではあります。
2019-07-30
三津田信三「魔偶の如き齎すもの」
刀城言耶ものの短編3作と表題作である書き下ろし中編を収録した連作集。
「妖服の如き切るもの」 クラシックなプロットに不可能犯罪が絡む、がっちりとしたミステリであります。真相前にいくつか出される仮説も、いかにも古きゆかしい探偵小説の興趣あるものだ。怪異と現象の絡め方はやや弱いかもしれないけれど、正攻法なパズルとして充分に楽しめた。
「巫死の如き甦るもの」 こちらは監視下からの人間消失。古典的なトリックの可能性を見せたまま、そこにはなかなか触れずに進んでいくので、読んでいてどうしても考えがそちらに引っ張られてしまうのがうまいところ。特異な状況を生かし、そこならではのロジック及びトリックが使われている。このシリーズのファンであればある長編で使われたアイディアに思い至るであろうが、今回はさらに強力なかたちで演出されているのがなんとも。中途までの怪奇色は希薄なのものの、終盤からの展開は実にえぐい。
「獣家の如き吸うもの」 じっくりとした怪談で始まり、ロジックで解体という形だけをとればとてもオーソドックスなミステリ。いささかすっきりし過ぎて、真相に余剰がないのが逆に物足りなく感じるかな。トリック自体は某古典作品のアレかな、と思わせておいて、そのまんまじゃないよ、というずれがあるもので、うまいものだ。
「魔偶の如き齎すもの」 ここでは怪異の味付けはそこそこ、特徴的な建物の中で起こる事件を扱ったフーダニット。中編のボリュームがあるので、独特な試行錯誤式の多重解決が堪能できるもの。それでいて、最終的な解決がそれまでとは違うベクトルから盲点を突いたものになっているのもいい。連作ならではの着眼点も面白い。
純粋にパズルとしてみれば「妖服~」が一番よくできてるかと。その他も、後味の強さは「巫死~」、怪異としては「獣家~」、ねちっこい推理は表題作と、それぞれテイストの違う楽しみがあって充実した作品集でありました。
2019-07-28
Billy Bremner / Bash!
ロックパイル第三の男、ギタリストのビリー・ブレムナーが1984年にリリースしたファースト・ソロ・アルバム。
内容はコンパクトで小気味良いパワーポップであるけれど、単純なギターコンボではなく、時代を反映したものかニューウェーヴを思わせるような鍵盤が目立ち、デジタルエコーも深い。そのためロックンロールとしての歯切れの良さはやや削がれているものの、耳当たりは決して悪くないサウンドで、コーラス・アレンジもあいまってジェフ・リン的なセンスを感じられる瞬間もある。
ブレムナーのボーカルは癖の無いキャラクターなので、生一本のギターロックにするよりも、こうした音の工夫でフックを作るのは正解なのかも。
収録曲はエルヴィス・コステロ作の "Shatterproof"、ディフォード&ティルブルック作で後にスクイーズのヴァージョンも発表された "When Love Goes To Sleep" の2曲以外は全て、ビリー・ブレムナーとプロデューサーのウィル・バーチの共作。それらオリジナルは'60年代ポップ的な展開のメロディが好ましく、だれるところもなしに通して機嫌よく聴いていられます。
コステロの曲は例によってメロディに対して言葉がやたらに詰まっているので、それと判りやすいな。また、"When Love Goes To Sleep" はスクイーズ版が未発表だったことを置いても、こちらのヴァージョンのほうがすっといいです。
難しい時代にすっきりとした落とし所をつけた好盤だと思います。ニック・ロウの「The Abominable Showman」やスクイーズの「Sweets From A Stranger」もこの程度に収まっていたらなあ、なんて考えたりもして。
2019-07-13
カーター・ディクスン「白い僧院の殺人」
1934年発表になる、ヘンリ・メルヴェール卿ものとしては第二長編、その新訳版。
謎の要は雪密室であり、これ自体の不可能性がかなり高い。そして、それを巡っていくつかの推理が開陳されていくのだが、これらも結構、手が込んでいて説得力もある。しかし、周辺をとりまくパズルのピースが効いていて、この解法を取ればあちらが成り立たず、的な複雑さがあって結局は否定されてしまう。
物語後半になってさらに事件が起こるものの、こちらはプロットの要請上という気がする。
ヘンリ・メルヴェールによって最終的に明かされるトリックは非常に良く出来ているがゆえに後の作家に影響を与え、却って今からするとその画期性は判り難いものになっている。もっとも大トリック一発の力に頼らず、意外性を最大限に生かすべく誤導が非常にしっかり作られているのは大したもの。まっさらな状態であたったなら、その衝撃はかなりのものになるだろう。
また、トリックが判ったからといって、全体が見えるということもない複雑な構図であり、さまざまな要素が実は緊密に組み立てられていたことがわかる、その絵解きはとても読み応えがあります。それでいて犯人の特定ロジックは実に明快、気持ちがいい。
トリックを成立させるために状況設定がややこしいものになっていて、そこがリーダビリティの足を引っ張っている感はある。しかし、オカルト色を排した純粋なミステリとして満足度はとても高いものでした。力作ですね。
さあ、次は『四つの凶器』だな。
2019-06-24
Van Duren / Are You Serious?
1978年リリース、メンフィスのパワーポッパーによるデビュー盤。制作はコネティカットにあるスタジオのよう。演奏の方は、ドラムとリードギター以外はだいたいヴァン・デューレン自身によるもの。
ぱっと聴きはラズベリーズっぽい。あれほどの派手さも華やかさもないけれど、節回しからはもろエリック・カルメンと思わされる瞬間はたびたび。メロディはマッカートニー系、あるいはトッド・ラングレンといったところの甘いけれど捻りがあってべたつかない筋のよさ。ギターサウンドからはビッグ・スターと共通するものを強く感じます。実際、クリス・ベルと組んで活動していたそう。なお、本人はエミット・ローズからの影響を口にしています。
アナログA面であるアルバム前半は「Inside」と題されているのですが、この部分が非常にいいです。
中でも抜群なのが "Grow Yourself Up" というマッカートニー直系(それもいいときのだ)の曲。グレイトなメロディに鍵盤オリエンティッドなアレンジが過不足なく嵌った。キレよく気合のこもった歌唱もあって、文句なくアルバム中のベストでしょう。
また、"Oh Babe" もパワーポップ王道といった感じの、ちょっと感傷をにじませたようなミディアムで、これもかなり良い。丁寧に作られた楽曲はなるほど、エミット・ローズ的ですね。
他の曲もしっかりとしたアレンジと良いメロディが聴けるもので、捨てるところがない。ギターサウンドの中に巧くクラヴィネットやシンセを絡ませたつくりは気が利いているし、凝ったバックコーラスやしつこいハモりはトッド・ラングレンを思わせるセンスです。
一方、「Outside」とされたアルバム後半はスロウが多めのせいか、やや地味な印象を受けます。また、曲によってはアレンジも中途半端というか中庸というか。楽曲そのものは悪くないのだけれど。
そんな中で気になったのが "So Good To Me (For The Time Being)"。わりと落ち着いた感じで始まり、徐々に盛り上がっていくスロウだが、バッドフィンガーですね、これは。サビなどももろピート・ハムじゃないですか。
また、"Stupid Enough" はアルバム中ではちょっと毛色が違うのですが、ごく初期のトッド・ラングレンのような、ローラ・ニーロ風ポップソングで悪くない。
強烈な個性こそありませんが、その分なかなか飽きがこない。良いメロディが揃った一枚。繰り返しになりますが、特に前半は素晴らしいです。
2019-06-17
ダシール・ハメット「血の収穫」
田口俊樹による新訳。この作品を最初に読んだのは田中西二郎が訳した版だった。後になって小鷹信光による訳文も出て、もうそれで十分だと思っていたのだが。小鷹訳からも既に30年経っているのね。
『血の収穫』は1929年に出されたハメットの長編第一作。物語の多くの部分はギャングの抗争のようなものであり、相当に荒っぽい。語り手である「私」──コンティネンタル・オプが結末で普通の日常に戻っていくことに違和感を覚えるほどである。ただ、「私」が法の向こう側に行ったきりであったら、それはノワール小説なのだけれど。
何もかもが腐敗しているポイズンヴィル。「私」は一介の調査員に過ぎない存在だが、恐ろしいまでの才覚と度胸を武器に街の顔役たちを嵌め、互いが対立するように仕向けていく。そして、ある時点でそれまでかろうじて成り立っていたバランスが崩れる。「私」の策略通りではあるが、もはや「私」にも事態のコントロールはできなくなる。また、「私」自身も状況に飲み込まれており、もはや自分で無いような感覚で、いったん理性のたがが外れたようになる。
しかし、なんとかぎりぎりのところで踏みとどまり、自分を取り戻したあかしを立てるように抗争の最後を見届け、更には殺人事件の謎解きを行う。見方を変えれば、謎解きをしっかりと書き込むことでハメットは、「私」というキャラクターを表現したということになりそうだ。
今回改めて読んでも、単純にエンターテイメント小説として面白い。その上で、後半の展開──スタイリッシュなクライム・ノベルがその形を一気に崩していくダイナミズムは異様だと思った。これはやはり『マルタの鷹』や『ガラスの鍵』のような三人称小説では描きえなかったものだろうな。
2019-05-19
エラリー・クイーン「Xの悲劇」
新訳クイーン、前回に予告されていたのは『シャム双子の謎』だったのに。また『X』か、と思ったのだが角川の越前訳が出てから既に十年経っているのね。
もはや読むのが何度目くらいかわからなくなっているのだが、面白かった。これよこれ、という感じ。こちらの読み方が歳を追うにつれて変化している分、新しい発見もあった。
注目していたのは探偵エラリーでは描けなかった、奇抜な個性を持つヒーローとしてのふるまい。それにしてもドルリー・レーンの王様っぷりよ。現実世界でも大舞台で主役を張ってみたい、という。本人は否定しているものの、事件を演出するために話を引っ張っている、犯人も被害者もレーンによって泳がされている、そういう感が残る。特にダイイングメッセージはレーンがいなければ無かったはずの謎であり、そのことについては少し満足気にも見える。これに味をしめて、後のシリーズ作では更に事件への介入を強めていくというのは満更うがち過ぎでもないだろう。
物語には勿論、古臭い要素はある。しかし、ミステリとしての構造、姿勢の美しさはちょっとやそっとじゃ揺るがない。こういうきちっ、としたパズルストーリーをもっと読みたいのよ。
たとえば第一の殺人、ある物証で一気に容疑者が絞られてしまう流れなど、実に格好いい。この時点で既に明らかだったのだ、レーンははったりをかましていたわけではないのだよ、というね。
2019-05-02
The Californians & Friends / Early Morning Sun: 60s Harmony Pop Produced By Irving Martin
最近'60年代のニッチなポップスをリイシューしている豪Teensvilleから出た、これはちょっと凄いコンピレイション。ごく一部のひとにとっては待望のものではないでしょうか。
カリフォーニアンズというグループはその名に反してイギリスのグループで、ビーチ・ボーイズ的な西海岸ポップを標榜していたよう。この盤には彼らが1967~69年に出した全シングル16曲に加えて、プロデューサーのアーヴィング・マーティンが手掛けた他のミュージシャンの曲が14曲収録されております。
なお、音質の方はぼちぼち止まりですね。板起しが多そうなのは仕方がないとしても、音圧がちょっと高過ぎるかと。
さてカリフォーニアンズ、音楽のほうは後期アイヴィー・リーグやホワイト・プレインズ、あるいはハーモニー・グラスあたりも思わせる、いかにも英国産のハーモニー・ポップ。
楽曲は殆どがカヴァーです。スパンキー&アワ・ギャング、ハプニングス、カウシルズ等々、米国ものでは本家と比べると少し抜け切らず、ウェットな感じが残るのは英国製の常ですね。英国内のヒット曲ではフォーチュンズの "You've Got Your Trouble" やクリフ・リチャードの "Congratulations" なんてやっていますが、いずれもしっかりとしたプロダクションと気合の入ったコーラスが楽しく、お手軽に作られたものではありません。しかし、聴き物はむしろ非有名曲のほうですね。中でもセンスのいい管の使い方やサビ前のリッチなコーラスが素晴らしい "What Love Can Do"、A&Mレコードあたりを意識しているようなラウンジ風ボサノヴァ "The Sound" が特に気に入りました。
ともかく三年ほどの間、全く売れなかったのにもかかわらず、音楽性にさほどブレがないし、創作意欲が落ちていないのは大したものです。もっとも、アーヴィン・マーティンというプロデューサーはヒットシングルをひとつも作っていないようなのですが。
カリフォーニアンズ以外の収録曲もそこそこいいのが揃っております。ポール・クレイグの "Midnight Girl" はジョン・カーターの書いた佳曲だし、ファインダーズ・キーパーズの "Friday Kind Of Monday" はエリー・グリニッチの曲で、こちらもいい出来です。あと、女性シンガーがいたロイヤルティというグループのものが5曲あって、これも悪くない。ペパーミント・レインボウやロジャー・ニコルズ&SCOFの曲などほぼコピーに近いのだが、しっかりしたものだ。
全体に良質な英国産ポップスが楽しめる一枚であります。トニー・マコウリィやクック&グリーナウェイが関わっていたグループのファンなら気に入るのではないでしょうか。
2019-04-30
A・A・ミルン「赤い館の秘密」
ギリンガムはまた低く笑い声をあげ、ベヴァリーの腕を取った。「きみって、じつにすばらしい相棒だよ、ビル。きみとわたしとでなら、なんでもできそうだ」
池はさえざえとした月の光をあびて、日中よりも荘厳なたたずまいを見せている。池を見下ろせる小高い丘の斜面をおおっている木々は、謎めいた沈黙を守っている。世界には、ギリンガムとベヴァリーのふたりしかいないような気になる。
新訳版です。1921年の作品ですから、クリスティもデビューして間もないくらいの頃になります。
作風としてはまっとうなパズル・ストーリーといっていいでしょう。他分野で名を成した作家による唯一の推理長編ということで、いかにもアマチュア的な楽しさが横溢。その一方で、ジャンル・プロパーの手による作品と比べるとバランスに妙なところが見られます。
扱っているのはカントリーハウスでの殺人なのだが、屋敷の滞在者たちは事件が起こって早々に帰宅が許されてしまい、以後は物語に顔を出さない。
また、事件発生当初より後は警察による捜査の描写が殆どなく、その進捗が知らされることもありません。ゆえに素人探偵とワトソンのディスカッションによってお話は展開されます。
どうもねえ、この作者は嫌なやつ、生々しく不愉快な場面を描くのを極力、避けていたのではないかという気がするのですよ。それがいいことなのか悪いことなのかは判りませんが。
ミステリの構成としては最初に事件があって、あとは調査・推理が繰り返されるのみなのですが、これが意外にも読みでがある。探偵ギリンガムは新しい事実が判明する度に、もったいぶらず自分の考えを打ち明けるので、局面の変化がダイナミックに現れていきます。推理自体の複雑さもなかなか、どうして、いいじゃないですか。
ただしその分、最終的な解決場面が薄くなってしまっています。真相自体が(今となっては)意外性のないもの。誤導に乏しいのも痛いところ。
欠点も挙げてきましたが、純粋に物語るのが巧いし、魅力的な場面もある。ユーモアも利いている。それらは推理小説としての面白さではないのかもしれないけれど。
2019-04-22
フラン・オブライエン「ドーキー古文書」
アイルランドはダブリンの海岸近くにある町、ドーキー。そこでミックは化学者にして宗教学者のド・セルビィという紳士と知り合う。ド・セルビィは時間の流れを司る発明に成功、さらには地球上の生命体を絶滅させる研究を進めているという。はじめのうち半信半疑だったミックであったが、およそ信じ難いような体験をさせられ、密かにド・セルビィの人類滅亡計画を妨害することを決心する。
1964年作品。白水社からは同じ作者の『第三の警官』、『スウィム・トゥー・バーズにて』も出されているが、それらよりもかなり後になって書かれた作品だそうであります。
設定は非常に相当に出鱈目で楽しいものだ。なにしろ、物語はじめから『第三の警官』の影のヒーローであったド・セルビィの登場となれば、期待してしまうのだが。枝葉の多いぐだぐだしたやりとりと、どこかのんびりした展開で、なかなか盛り上がらない。宗教談義が多いのも、わたしにはピンとこなかった。
物語後半に入るとジェイムズ・ジョイスそのひとまでが現れるのだが、さて。
ユーモラスな要素には事欠かないものの、なにしろオフビート。お役所に勤める主人公は人類の危機に接している筈なのに、日が落ちたら残りは全て後日に、といった風情であります。いくつかの大問題の往く末も実に間の抜けた、エンターテイメントの常道を予想して読んでいたら唖然とさせられる処理であります。
およそファンタスティックな要素が最後にはうっちゃられ、居酒屋にてみんなで良い気分。定型的なドラマツルギーの拒否が逆に痛快、非日常をおちょくっているようなそんな物語でありました。
2019-04-14
Curtis Mayfield / Keep On Keeping On: Studio Albums 1970-1974
今年Rhinoからリリースされた、カーティス・メイフィールドの4枚組。中身はオリジナル・アルバム「Curtis」、「Roots」、「Back To The World」、そして「Sweet Exorcist」のリマスター。ボーナス・トラックは収録されていないし、ブックレットもついていない簡素なつくりです。
タイトルが「Studio Albums 1970-1974」なので二種類のライヴ盤は入っていません。「Super Fly」が入っていないのもサントラだからかな。しかし、「Got To find A Way」も1974年のアルバムなのだがな。残りのカタログもいずれ、まとまったかたちで出してくれるというのならいいのだけれど、どうも内容量には不満です。
音のほうはさすがにRhino、ちゃんとしています。特に「Back To The World」と「Sweet Exorcist」はおそらく、まともなソースからのリマスターは世界初ではないでしょうか(カーティスの遺族によれば、英Charlyが出しているのはブートレグだ、とのこと)。この二枚だけでも価値はあるのでは。
「Sweet Exorcist」は1974年にリリースされたアルバム。それまでと比較すると、派手さの無い落ち着いたサウンドで、管弦も使われているのだがやや控えめ。その分、基調となるグルーヴや微妙なアレンジを聞かせるものになっているのだが、曲によってはいささかベースがうるさくて、それが軽快さを損なっている印象も受けます。
それぞれの曲は丁寧に作られていて、特にアルバム前半の流れが凄く良く出来ている。
中でもメロウなタイトル曲 "Sweet Exorcist" ではボーカルの重なり具合など、繊細なアレンジが凄く好みです。
また、アナログA面最後に当たる "Power To The People" のポジティヴな曲調はアルバム中で一番コマーシャルかも。クラヴィネットが印象的です。
シングルになったファンク、"Kung Fu" にはブラックスプロイテーション的なアレンジの管弦が施されているが、主役はあくまでグルーヴだ。しかし、ちょっと硬派すぎるかも知れんね。
ドニー・ハサウェイとの共作、"Suffer" は元々1969年に出されたホリー・マクスウェルという女性シンガーのシングル曲。スロウでも微妙にリズムが跳ねているのがシカゴ流儀かしら。
時代に向き合うためによりオーソドックス、もしくはカジュアルな表現を取り入れ、それを独自のスタイルとブレンドする試行錯誤。それが重さになることもあれば、感動的な表現に結びつくこともある、そんな感じ。
2019-03-24
Rupture / Israel Suite/Dominante En Bleu
1973年、カナダ人ドラマーが中心となってフランスで制作したアルバム。オリジナルは少数枚のプライヴェート・プレスだったそうなのだが、権利関係がややこしいことになっているようで、Discogsのレヴュー欄ではリイシュー会社同士でやりあっていて何だか。
肝心の内容の方ですが、大雑把にいうと歌物のヨーロピアン・ジャズ・ファンク。深いエコーが特徴的で、クールなエレピが気持ちよく、スタンダップベースの太い響きも効いている。そこにブラジル的でメロウなメロディが乗っかる。歌詞はフランス語なり。
アナログではA面全体を占める "Israel Suite" は18分余に及ぶ組曲。フュージョンというかジャズロックって感じの演奏はキメもあればフリーでアブストラクトなソロもあるし、オーセンテイックなピアノトリオのようなパートもある。さまざまな局面を見せながら、しかし、歌の部分がしっかりとポップソングで、終盤には結構ドラマティックに盛り上がる。初めて聴いたときはピンとこなかったのだが、この展開を飲み込んでからは良くなってきた。
アルバム後半はコンパクトでわかりやすいものが5曲並んでいる。
ボーカルパートが少ない "Alice Aux Miroirs" は丸っきりフュージョンといって差し支えないものであるし、一方でアコースティック・ピアノが使われた叙情的スロウ、"Entre Ses Cils" はシンガーソングライターものを聴いているようである。
それらの中でも "Mes Histoires Bleues" は疾走感あるジャズファンクで、そこにメランコリックなメロディがはまっている。よく転がるエレピも気持ち良く、どれか一曲というと、これが一番格好いいかな。
クールで都会的なジャズファンクをベースにしながらメロウなポップであり、結果としてプログレとシティ・ポップを縦断してしまっているようでもある。おしゃれフレンチというにはちょっと尖り過ぎていますが、そこもかっちょいい。
しかし、特定のジャンル・プロパーのひとは受け付けないかも知れんね。節操の無いリスナー向けという気はします。
2019-03-09
R・オースティン・フリーマン「キャッツ・アイ」
1923年作品でソーンダイク博士もの。
宝石「キャッツ・アイ」を狙った強盗殺人があり、その犯人たちのひとりを目撃した女性の命も狙われる、というお話。
読み物としては流石に古風です。その中でも大きいのは過去の因縁話と現代の事件を絡めるやり方ですね。ロマンといえばそうなんだけれど、そのセンスからは前時代的な印象を受けます。クリスティ以前、ドイルの時代というね。
また、ヒロインが危険に晒される場面やロマンス部分など型にはまったものでしかないように思いました。物語中盤あたりはだれてしまって、なかなか読み進める気にならなかったのが正直なところ。
一方、ミステリと面はとてもしっかり作られています。ロジックの飛躍には乏しいものの、手掛かりの圧倒的な量もあいまって、こうでしかないという説得力があります。さりげない伏線ではなく、はっきりとした証拠ばかりとあって、力強い。特に物語の序盤に示された手掛かりが決定的な意味を持っていた、というのは個人的にしびれるところであります。
また、フーダニットとしてはたしかに意外性はないけれど、犯人の属性には十分に意外性を考慮した(この時代としては、ですが)ものであると思います。
現在の感覚からすると冗長なのですが、まあクラシック作品を読むようなひとは、むしろそこを愛でるのかな。
実の詰まった力作ではないかと。
2019-02-11
Utopia / Deface The Music
トッド・ラングレンのユートピア、1980年のアルバムはビートルズのパスティーシュというかオマージュというか、そういうもの。
しかし、改めて聴いてみるとメロディやアレンジはともかく、楽器の音色やミックス等、サウンド面からはそれほど似せようという意識は感じないですね。鍵盤とか嘘みたいだ。トッド・ラングレンはソロの「Faithful」で'60年代の有名曲のコピーを披露しているので、もっとやろうと思えば出来たはずですが。ソロとグループの違いでしょうか、マニアックな楽しみよりダイナミズムを優先したのかもね。
このアルバム、ビートルズの音の変遷をたどるような構成になっていて、初期ビートルズを意識した曲では、なるほど、それっぽいなあ、と思うわけですね。けれど、アナログB面にあたる後半のほうになると、別にビートルズ云々がなくても楽しめるポップソングも多いんですよ。"Hoi Poloi" なんて後のジェリーフィッシュみたいだし、"Always Late" はビートルズよりもスタックリッジに近いんじゃないかな。また、サウンドでいうと "Feel Too Good" はXTCの「Skylarking」のそれと共通するものがあります。
判りやすいかたちでのトッドらしさは希薄なのですが、実のところ多岐にわたるユートピアの音楽の中で、個人的にはこのアルバムが一番肌に合うのですね。
2019-02-09
アンソニー・ホロヴィッツ「カササギ殺人事件」
舞台は1955年の英国。病気により余命2、3ヶ月となった名探偵アティカス・ピュントは残された時間を静かに送るため、もう事件の依頼は受け入れないつもりでいた。しかし、田舎の小さな村からロンドンまではるばるやってきた若い女性の相談──婚約者が自分の母親を殺したという疑いの目で見られている──に、つい耳を傾けてしまった。
昨年、一番話題になった翻訳ミステリなので、とりあえず読んで見た。結論からいうとわたしはそれほど感銘を受けなかったのです。
ます、アラン・コンウェイ作『カササギ殺人事件』なんですが、こちらはオーソドックスなフーダニットとしてとても楽しく読めました。
最初の事件の真相はまあ、見当が付きやすい(というかクリスティのパスティーシュならこうなるだろう、という)もの。
そして第二の事件のほうなのだが。なるほど過去にあった出来事を読み解くことで現在の事件の構図が明らかになる、というのはいかにもクリスティらしい趣向ではあります。解決編のプレゼンテーションも良い。まず、ひとつひとつはそれほどでもない伏線を、しかし大量に回収していく。見事ではあるけれど、これらはまだ、そうであれば綺麗に収まる、というレベルにとどまるもの。だが、最後になって些細だけれどこうでしか説明できないという事実を出してくる。これにより、全体がびしっと締まりました。
純粋に謎解きだけをとればクリスティの水準作を上回っていると思います。ただし、ストーリーテリングやパズルがドラマを生み出すという点ではそこまではいかないかな。
一方で作中の現実パート、小説『カササギ殺人事件』をめぐって起きる事件のほうは、まあそこそこというか。こちらの登場人物が作中作のモデルになっていたりするので、事件の手掛かりも作中作に忍ばされているのではないか、とわたしは勝手に思ってしまったのだ。
このパートの仕掛けとしては遺書のトリックがメインだと思うのだが、いくら何でもヒントを出し過ぎである。ああ言われれば読み返すし、読み返せば気付くよ、そりゃあ。
あと、犯人はそもそも結末だけでなく原稿全体を抹消してしまえばよかったんじゃないの、と考えたのですが、どうかしら。
悪くはないけれど、期待し過ぎたのかなあ。上巻を読んでいるときはなるほど、これはいいぞ、と思っていたのだけれど。
2019-01-27
Classics IV / Spooky/Mamas And Papas Soul Train/Traces/Song
昨年の暮れに英BGOよりリリースされたクラシックス・フォーの2CD。1968~70年にかけてImperialおよびLibertyから出た4枚のアルバムをまとめたものであります。
彼らの場合、コンピレイションはいくつか出ていたのだけれど、なぜかオリジナルアルバムの形でのリイシューは(怪しいものを除けば)これまでされてなかったので、これは待たれていたのではないかしら。
ファーストの「Spooky」はタイトル曲がヒットしたことを受けて急造されたのか、その "Spooky" を除くと、それほど大したことが無い。オリジナルと有名曲のカバーが半々で、中ではスタンダードの "You Are My Sunshine" のファンキーな仕上がりがユニークというか何と言うか。ボーカルはジェイムズ・ブラウンの物真似だし。一方、オリジナルの "Poor People" は純然たるハリウッドポップ。この曲や次の "Book A Trip" なんて聴くと、やはりスタジオ・ミュージシャンの演奏だよな。
他にはデニス・ヨスト以外のメンバーがリードボーカルを取っている曲もあって、まだスタイルがまとまっていない感じがします。
セカンド「Mamas And Papas/Soul Train」になるとオリジナル曲が中心になり、プロダクションもしっかりしたものに。全体にソウル色を感じさせるアレンジ、歌唱が聴けるものが多く、特にスロウの "I Pity The Fool" など堂々としたものだ。ヒットした "Stormy" でのエレクトリック・シタールの使用もソウル的な流行から考えればしっくりくるな。また、わざわざ "The Girl From Ipanema" までファンキーに料理しているのだが、これが悪くないのだ。
ソングライティングの面では "24 Hours Of Loneliness" あたりに洗練というか、よりポップな方向へ向かう兆しが見えています。
1969年に出たサード「Traces」はぐっとミドル・オブ・ザ・ロードな方向へシフトした内容。ストリングスも入って、ロックバンドらしさは薄くなっていますが、その分ポップスとしては迷いがないとも言えます。アルバム4枚のうちどれか、といえばやはりこれになるかな。中ではトミー・ロウの "Traffic Jam" が軽快なサンシャイン・ポップであって、特に好みですね。
翌年の「Song」はImperialの親会社であるLibertyよりリリース。ジャケットにあるのはデニス・ヨストの顔だけであり、ヨストの名前がグループ名より大きく記されています。
音楽のほうはゴージャスなオケをバックにソロシンガーがしっとりと唄い上げる、という感じで、ときおりB.J.トーマスあたりに近い印象も受けます。全体に曲の粒は揃っていると思うのだけど、個人的にはやや落ち着き過ぎかな。都会的な面を強調した "Midnight" や、ブルー・アイド・ソウルとして聴ける "Pick Up The Pieces" なんていいですけれど。
ヒット曲だけ取ると似たようなものばかりながら、アルバム単位で聴くと短い期間のうちにも音楽性にはある程度、変遷があるのが感じられます。その初期においてはバンドとしての雰囲気を残していたのが、最後にはデニス・ヨストのソロといってもいいようなムード歌謡になっていくという。
あと、ライナーノーツを読んで知ったのですが、大ヒットシングルをいくつも持っているわりには、これらのアルバムはさっぱり売れなかったようであります。そういったところもリイシューが遅れていた理由かもしれませんね。
2019-01-03
Johnny Mandel / M*A*S*H (original soundtrack)
1970年のいわゆるニュー・シネマ、そのサウンドトラックであります。映画のほうは昔テレビでかかったときに一度見たことがありますが、あまり印象が残っていない。個人的に良く覚えているのはテレビドラマシリーズのほう。もっと思い入れがあるのはリチャード・フッカーの原作小説ですね。
この盤はいかにも古い時代のサントラらしく、劇中のダイアローグが盛り込まれているのですが、曲中にも会話が割り込んでくるので、純粋に音楽を楽しむにはあまり向かないのです。ジョニー・マンデルによる劇伴曲のほか、日本の古い歌も入っていて面白いのだけれどね。
テーマ曲は "Suicide Is Painless" で、さすがにこれは余計な邪魔もなく聴けます。パセティックなフォークロック調の曲で、レターメン風の男声ユニゾンがハーモニーへと変化していくさまが美しい。歌っているのはベイラー兄弟らL.A.のセッションシンガーたちで、まあ、聴き所というとこの曲に尽きるのですが(シングル盤も良く売れたそう)。さて、ここからが本題。
1973年にアーマッド・ジャマルがこの曲をカバー、シングルでリリースしている。リチャード・エヴァンズがアレンジを手掛けたこれがえらく格好いいジャズファンク。翌年のアルバム「Jamalca」にも収録されているらしいのだけれど、これが全く再発の対象にならないのだ。
ところが、このジャマルのヴァージョンが「MASH」のサントラ、その1973年の再発盤でコーラス・ヴァージョンの代わりに収録されたのだから妙な話。現在出回っている「MASH」の廉価版CDでもボーナストラック扱いで聞くことができるのは非常にありがたいのだが、サウンドの質が全く異なるのでなあ、「Jamalca」も出してよ、とは思う。
登録:
投稿 (Atom)