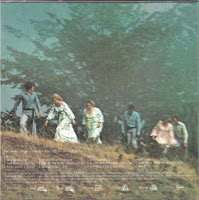2018-12-22
G・K・チェスタトン「奇商クラブ」
1905年発表、チェスタトンのキャリアでも初期の連作短編集、その新訳。
タイトルの奇商、というのは原題では「Queer Trades」で、奇妙な商売ってことである。入り組んだロンドンの市街に存在するという会員制の「奇商クラブ」、その入会条件はこれまで誰もやっていないし、既存のものの応用でもない商売で生計を立てている、というものだ。
物語の中心となるのは発狂した元判事のバジル・グラント。彼の友人である語り手と、半ば趣味で探偵をやっているグラントの弟がその他のレギュラー・キャラクターである。
各編において、どのような商売がひそかに営まれているのか、というのが読者にとっての謎ではある。しかし、作中人物たちはそういったことについては意識していないのだ。犯罪を匂わせる奇妙な事件に首を突っ込んで(あるいは巻き込まれて)いるうちに、お話のなりゆきでその商売が明らかになるという構成である。それぞれの真相は趣向を凝らしたものだが、グラントがどうした過程を踏んでそこに辿り着いたかは説明されないので、謎解きの興趣は薄い。
一方で、陰惨な事件は起こらないので、読後感は明るい。その奇抜な展開も逆説として捉えるより、ユーモア小説のそれと受け止めたほうがお話としては飲み込みやすい。
収録された6作のうち、前半の3作がそのへんてこな商売や愉快なプロットでストレートに読めるものになっている。後半になるとチェスタトンならではの世間離れしたロジックが出始めていて、「おお、来たな」と思わされるのだが、チェスタトンの作品に親しんでないひとが読んだらわけが判らないかもしれない。
中では、「牧師さんがやって来た恐るべき理由」が特に良いです。馬鹿馬鹿しいお話にリアリティを持たせる説得力のある語りが魅力的。実に人を喰った展開も楽しい。
チェスタトン流〈日常の謎〉というか。これもチェスタトンしか書けない類のお話ですね。軽めではあるけれど、面白かった。
2018-12-16
The Reflections / Love On Delivery
ニューヨークのボーカルグループによる唯一のアルバム、キャピトルからのリリース(1975年)。プロデュースはJ.R.ベイリーと彼の「Just Me 'N You」に大きく手を貸したケン・ウィリアムズ。アレンジは全10曲中6曲がメイン・イングリーディエントを手掛けたバート・ディコートーで、4曲がホレス・オットー。
このグループはシングルが一曲、R&Bチャートでトップテンに入っただけの存在なので海外ではさほど人気はないのでしょうが、ここ日本に限っては何度かリイシューがなされてきました。
ボーカルグループとしてはハスキーなハイテナーのリードが特徴的です。熱っぽく、ラフな歌声は端正なバックとのコントラストで良く映えています。
ニューヨーク録音であっても、音のつくりはフィリーを強く意識したもの。特にミディアム・ダンサーでそれが顕著で、オープナーの "Day After Day (Night After Night)" なんてまるっきりスピナーズだし、"Telephone Lover" なんて歌いまわしもフィリップ・ウィンだ。時代的にややディスコ入りかけであって、個人的な好みのサウンドからは少しずれているものの、まあ相当に良く出来ています。
作曲は全体の半分がプロデューサーのベイリーとウィリアムズによるものですが、あと半分はリフレクションズのメンバー自身によるオリジナル。後者でもスロウの曲にはいいものがあります。"Now You've Taken Your Love" はサビ終わりの転調が洒落ていて、コーラスのトップがファルセットになるところなどたまらない。同じくスロウの "One Into One" もオーソドックスでありながら雰囲気たっぷり、実に聴かせる出来栄え。ミディアムでは "Are You Ready (Here I Am)" のイントロのつくりや、歌のバックでリズムがストップするアレンジが印象的で、よく考えられていると思う。
ベストとなるとやはり "She's My Summer Breeze"。これだけが陰影の深いニューソウルといった趣で空気感が違う。まあ、もろ「Just Me 'N You」の音世界なのだが。
2018-11-25
Hugo Montenegro / Lady In Cement
フランク・シナトラ主演の私立探偵もの映画「セメントの女」(1968年)、そのサウンドトラック盤。リイシューは2002年に英Harkitから。ボーナストラックとして別テイクが二つに出演者のインタビューが入っております。
Harkitという会社、評判は必ずしもよろしくない。音源がアナログ起しだったり、他社から限定で出ていたもののコピー臭かったり、あるいは権利をクリアしていないものを発売していたり。しかし、レアなタイトルを持ってくるので、なかなかに悩ましい。
この「Lady In Cement」も他所はどこも手を出してこなかったのだ。音質のほうはそこそこで、我が国の紙ジャケリイシュー専門の会社とどっこいってところ。
音楽そのものはとても良いのです。11曲中3曲は古い映画の挿入歌で、甘いムードのものでもしつこくなく、さらりと仕上がっているのは流石。そして、残りは全てヒューゴ・モンテネグロ自身のオリジナル。サスペンスを掻き立てるような都会的でジャジーなものや、いかにも'60年代らしい軽やかで優美なラウンジ調、荒々しいアップ(ハル・ブレインが大活躍だ)などさまざま。いずれもカラフルな音使いが楽しい。
中でも特に良いのが、ベイラー兄弟と思しい男声スキャットが涼しげな2曲。テーマ曲 "Lady In Cement" ではハープシコードがクールな雰囲気を強めているようで実に効果的だし、"Tony's Theme" でのバカラック的な管アレンジも洒落ている。こういうのばっかりだと、また飽きてくるのだろうけれど。
アレンジを生業としていたプロにとっては、さまざまなジャンルなど素材のひとつに過ぎないわけで。その自然な加工っぷりが音楽家としての大きさを示しているようで格好いい。
サントラやイージーリスニングには巨大な実験場としての面もあったのではないか、などと考えてしまった。
2018-11-04
The Action / Shadows And Reflections: The Complete Recordings 1964-1968
アクションのコンプリート集4CD。再結成以前の音源は一通り入ってます。英Cherry Red傘下のGrapefruitからのリリースで、監修は実績と信用のアレック・パラオだから、まず安心。
ブックレットも写真満載かつ、グループの歴史がしっかり書かれたもので、レコーディングのデータやエピソードも細かくあって、読みでがあります。
しかし、CDの収納が独特で、ちょっと面食らった。トレイ真ん中に爪がなくて、周辺部を押して引っ掛けるタイプ。耐久性に不安を感じるのですが。
ディスク1は「ESSENTIAL ACTION: THE PARLOPHONE MASTERS」と題され、ジョージ・マーティンの手掛けたスタジオ・レコーディングとBBCセッション5曲の全22曲がモノラル・ミックスで収録。
彼らのシングル曲の殆どについては、そのオリジナルのミックスでは初のCD化となります。これまでは'90年に作成されたリミックスがずっと出回っていたわけです。とりあえず、これがアクションのスタンタードであるよ、と。荒々しさだけでなく、しなやかさを感じさせるR&Bの消化の仕方が実にモッズど真ん中、という感じで粋ですなあ。
BBCのほうは(ここに収められた分に関しては)音質良好、モータウンやバーズのカバーも演ってます。
ディスク2は「THE ACTION AT ABBEY ROAD: STEREO MIXES AND OUTTAKES」。ステレオ・ミックスが15曲にリハーサル、別テイク、バッキング・トラックらで計24曲、全てが初登場となります。
これらは新規にマルチトラックよりミックスされただけあって、すごくクリアな音質です。息遣いのようなものが生々しい。今回のリリースでの一番の収穫でしょう。また、リハーサルのラフな感じも中々の格好良さ。ボーカルもシングル・トラックだし、曲によってはアレンジの違いも聴けて良いです。
ディスク3は「ROLLED GOLD PLUS: THE LOST 1967-1968 RECORDINGS」。「Rolled Gold」もしくは「Brain」といったタイトルで'90年代半ばに出された音源が15曲に、レグ・キング脱退後の曲が5曲(これらは1985年に「Action Speak Louder Than...」としてリリースされましたが、メンバーには無断であったとのこと)。
「Rolled Gold」は元々がモノラルのデモテープ、それをコピーしたものであり、曲によってはアセテートから起こしたとあって、やはり音質には幅があります。なお今回、編集の違う複数のソースからできるだけ長いものを選んだ、とは記されています。また、いくつかの曲はこれまでのものよりテープ・スピードを適正にした、とも。
スモール・フェイシズとプリティ・シングズの間を行くようなこれらサイケ・ポップは今聴いても十分に格好良いっす。
ディスク4「EXTRA ACTION」はここまでに入らなかった残りをさらったという内容。
前身バンドであるボーイズの曲から、デッカでのオーディション音源、BBC出演時のもの(こちらの音質はまちまち)が12曲目まで。あとは尺が余ったのか1990年にEdselからリイシューされたときに作られたミックスから8曲が選ばれています。
BBCでも実際に客前で演ってるものは熱が違いますな、うむ。あと、Edselミックスは改めて聴くとエコーが深くて、オリジナルと比べるといじった感があるかな。
しかし昨年のクリエイションといい、アクションまできちっとした形でまとめてくれたので、個人的にはもう目ぼしいところは残ってないかも。
2018-10-21
青崎有吾「図書館の殺人」
高校生、裏染天馬が探偵役を務めるシリーズの第三長編。文章はかなりこなれているし、パズラーとしても来るとこまで来たという感じで、平成のクイーンの名に恥じない出来栄え(平成はもう終わっちゃうけど)。一見わかりきったようなことでも、その過程をねちっこく検証するうちに意外なことが明らかになっていく、その手つきが堂に入っています。
また、ダイイング・メッセージを巡る推理が凄いですな。現代にあえてこの趣向を扱うなら、ここまでやりきらなくては面白くないよね。
消去法が進むうちに容疑者が全ていなくなってしまう。そして、そこから急転直下の犯人確定。探偵小説ファンにはしびれる展開だ。しかし、伏線がよほど巧くないと、それまでに展開された推理全体の強度を疑わせるものになりかねない。また、読者が「それアリだったら、他にも可能性があるじゃない」と考える余地も出てくる。今作はそのあたりが不十分だと思います。
あと、一番鮮やかだったのが、ある手掛かりが犯人による偽のものだということを証明する場面だったのだが、この証明によって大きく何かが変わったかというと、そうでもないような気がする。
ケチを付けましたが、それだけレベルが高いということなので。もっと、もっととなってしまったのです。
犯行動機の収まりはいい。謎と論理の物語としては、確定できない事柄について、これ以上はやりようがないだろう。
また、物語としての締めもこの作品ではすべっていない。実にきれいに決まっています。
うん、めちゃくちゃ面白かった。
2018-10-20
Leroy Hutson / Love Oh Love
今年になって英Acid Jazzより、リロイ・ハトソンがCurtomに残したカタログがリイシューされています。ディスコの「Unforgettable」以外は購入していますが、シングル曲等のボーナストラックが付いて、マスタリングもちゃんとしたもの。音圧がでかくないと不満なドンシャリ耳のひとが気に入るかは知らんけどさ。
ファーストの「Love Oh Love」は1972年のリリース。ファーストといっても裏方も含めると既に充分にキャリアがあったので、しっかりとした作品に仕上がっている。
音のほうはゴージャスながらオーソドックスなシカゴ・ソウルという感じ。アレンジはいくつかの曲でトム・トム84やリッチ・テューホが手を貸しているが、それ以外はハトソン自身によるもの。カーティス・メイフィールドやマーヴィン・ゲイを思わせる部分はあれど、後の作品のように、もろにアレだな、というところが少ないので、落ち着いて聴いていられるし、インプレッションズでリードを取っていたひとのソロだ、と考えても違和感はない。色の無い歌声もここではオケに負けずに収まっているように思う。
リロイ・ハトソンの音楽は凄く良く出来ているけれど、強い個性には乏しい。その変化も時代とともに作っていくというより、流行に敏い、というのが的確なところだ。肉体性に乏しい歌声もあってか、後味を残さない。だが過剰なものがない、そのことはこのひとの美点でもある。
昔は、このオケにもっとディープなボーカルが乗っかってればなあ、などと感じていたのだが。いや、これでいいのだ。
2018-10-13
フィリップ・K・ディック「いたずらの問題」
舞台は2114年、相互監視による道徳的行動への縛りが強く、そこから外れるものは吊るし上げられたのちにコミュニティから排除される、そんな社会。そして、社会全体の「モレク」を管理する委員会は、風紀を維持するために広告代理店の作った物語を採用している。
それら代理店のうち業界最後発のものの社長、アレン・パーセルが物語の主人公。ある朝、パーセルが出社するとこれまでなかったことに、委員会の書記の訪問を受ける。アレン・パーセル社が提出した「パケット」のひとつに問題があるというのだ。
1956年だからキャリア初期の長編。創元推理文庫版で読んでいるはずなのだが案の定、あまり覚えていない。訳者は同じながら、今回、早川から出るにあたって新たに手を入れてあるそうです。
内容は典型的なディストピアもので、SFとしてはやや地味。監視社会におけるサスペンスとして中盤くらいまでは展開していきます。権力の設定、ガジェット、悪夢的なツイストなどからは、いかにもディックらしいセンスが感じられるけれど、後年のディック作品のような、そこから一気に突き抜けていく部分もない。ただ、落ち着いた筆運びは、感情的な説得力を持たせるものだ。プロットにも余計な要素が少なく、まとまりがあって、わかりやすいお話になっています。
また、ディック本人は60年以上前、米国ではなくある全体社会国家をイメージして執筆したそうなのだが、ここで描かれている社会はデフォルメされてはいても、かなり現代的なものとして受け取れる。
物語後半、パーセルが追い詰められてからの反撃は(直球すぎるきらいはあるものの)、トリックスター的で娯楽性が高い。そして、それだけに結末はしんどいなあ。
しかし、フィクションとして振り切ってしまわずに、とどまったうえで希望の身振りを示すのもディックらしさではあるか。
2018-09-30
Milton Wright / Complete Friends And Buddies
ミルトン・ライトのアルバム「Friends And Buddies」(1975年)、そのごく少数出回ったというファースト・プレスと、内容に手を入れたセカンド・プレスをまとめたうえにボーナス・トラックもつけた完全盤。
ふたつのヴァージョンの違いだが、セカンド・プレスではシンセがオーヴァーダブされて、ミックス・バランスもかなり変わっている。また、最初のには間に合わなかった "Keep It Up" という曲が差し換えで入っている。
個人的にはファースト・プレスのほうが断然好みで。サウンドが生々しくってずっと現代的。メロウネスとエネルギーのバランスが素晴らしい。一方、セカンド・プレスはシンセによるスペイシーな感触が加わっている。悪くはないけれど、やはり時代の音という印象がする。"Keep It Up" はいかにもマイアミ・ソウルらしいけだるさと湿度を感じさせるメロウなミディアムだが、ややディスコ入ってるかな。
収録曲はどれも弛みなく作られているのだけれど、特にタイトル曲の冒頭で聴ける女性コーラスの豊かな響きが、もうなんともたまらない。ミルトンのマニッシュな歌声との対比も実に格好良い。
また、キャッチーなミディアム "My Ol' Lady" はアイズリー・ブラザーズを思わせて、これもまろやかなグルーヴが心地いい。
セカンド・プレスからは漏れたのが "Nobody Can Touch You"。アコースティックでビル・ウィザーズ風といえるか。これにはシンセは入れ難そうだし、そのままだと流れから浮いてしまうから外されたか。
ミルトン・ライトの歌唱はスティーヴィー・ワンダーの影響が伺えるラフなものだけれど、朗々と歌い上げる局面もあって、あまりソウルっぽくない。ゆったりとした地中海岸的なリズムアレンジの曲なんかでは、その歌唱もあいまってジョン・ルシアンを想起したりもする。
個々のパーツだけを取り上げるとそんなに個性はないのだけれど、その纏め上がりがオリジナルというね。グレイトな盤です。
2018-09-17
有栖川有栖「インド倶楽部の謎」
インド風の意匠が凝らされたその屋敷では、程度の差こそあれインドに関心を持つ人々による集いが定期的に開かれていた。あるときの会合に於いて、本場の先生を招いた「アガスティアの葉」のリーディングが行われる。「アガスティアの葉」には全ての人間の死ぬまでの運命のみならず、前世までもが記されているという。
数日後、その場に立ち会った人物が相次いで死体で発見される。
作家アリスものの新作。あいかわらずうまい。ファンタスティックな設定の自然な導入もそうだし、突っ込みをところどころで入れることで、逆に作品内でのリアリティを補強しているのだと思う。また、ICレコーダーやポチ袋といった小道具の使い方もいいなあ。
大きな謎のひとつは中盤あたりであっさりと明かされる。いったいに探偵小説を読んでいると捻ったようなロジックや、予想外のトリックに飛びついてしまいがちなのだが、それらを餌にしつつ最短距離を結ぶシンプルな解を提示されると、虚を突かれたようになってたまらない。
フーダニットとしては難しいバランスの上に成り立っているという感じ。関係者は揃ってアリバイがないので、動機探しが大きくなっているのだ。
共同幻想に取り込まれたゆえの事件、というのはとても現代的であると思います。そして、その種を蒔いたのが被害者自身である、という構図も実に良く出来ている。ただし、この部分が謎解きのメインを占めていながら、犯人確定の手掛かりはまた別のところにある、その辺りを物足りなく思う人はいるかもしれんね。
特異な前提を解体していきながら、最後まで割り切れない部分が事件の核であった、というのがミステリとして美しいと思います。個人的には満足して読めました。
シリーズの愛読者としては野上巡査部長の単独行パートも興味深かった。普段、ぶっきらぼうな野上が何を考えているのか、火村や有栖川の存在をどう捉えているのかとか。
2018-09-02
ヘレン・マクロイ「悪意の夜」
夫を事故で亡くしたばかりのアリス。遺品を整理していたところ、「ミス・ラッシュ関連文書」と書かれた封筒が見つかる。おそるおそる開いてみたが、中身は空。そうこうしているうちに息子がタチの悪そうな美人を家に連れてくる。彼女の名前はクリスティーナ・ラッシュだった。そのクリスティーナはアリスの夫とは会ったことがない、と言うのだが。
1955年の作品で、ベイジル・ウィリングものとしては最後の未訳長編ということ。
アリスはクリスティーナのことを疑い、さらには憎みつつも、自分の判断に確信を持てないでいる。さらにはマクロイ作品ではお馴染みのある趣向も出てくる。読者もアリスのことを信用しきれず、どこかでちゃぶ台をひっくり返されそうで、気が抜けない。半ばニューロティック・サスペンスのように物語は進んでいきます。
しかし、なんだか全体に駆け足なのです。アリスはよく気を失い、そのたびに流れが途切れ、展開が変わる。テンポがいいと言えなくも無いが、なかなか雰囲気が醸成されない。また、クリスティーナの悪女ぶりもあまり伝わってこないんですね。実際のところ、アリスが受けた印象以上のものがない。読んでいて、こんなことを言われたら、そりゃあ態度が悪くなっても仕方ない、と思ったもの。
そして、残念ながらフーダニットとしてはごく平凡なものでありました。前半部分の思わせぶりが、それ以上のものではなかったのは痛い。
推理の妙味にも乏しいです。なにしろ容疑者は少なく、誤導も少ない。読んでいくうちに動機のおおよその種類は見当が付くので、自然と犯人も絞り込まれてくる。また、決定的な手掛かりは解決直前まで判明しない上に、最初の事件が犯罪であったという証拠は結局、無いままだ。
一方で、失われた書類のありかは法月綸太郎のある短編を思わせるし、犯人の意図したところが丸っきり裏目に出てしまうところなどは面白いけれど。
サスペンスと謎解きがうまく混ざらなくって、結果、どちらも中途半端になったように思いました。マクロイにしては水準以下でしょう。シリーズ全てを日本語で読めるようになったことはありがたいけれど、残り物には福が、とはいかなかった。
2018-09-01
Buffalo Springfield / Last Time Around
バッファロー・スプリングフィールドの3枚目にして最終作、1968年のリリース。
基本的にメンバーがばらばらに録音した曲や以前からの残り物をレコード会社との契約履行のためにひとつに纏め上げたアルバムです。プロデューサーにはジム・メッシーナがクレジット。
ニール・ヤング、スティーヴン・スティルス、リッチー・フューレイのうち関与の割合が一番少ないのがニール・ヤング。凄く良い曲をふたつ書いているのだけれど、リードを取って歌っているのが一曲なので、アルバムの流れの中ではその存在があまり印象に残らない。あとはスティルスとフューレイが半々という感じだがジム・メッシーナの曲もひとつと、ラジオ局主催のコンテストで一般から選ばれた曲、なんてのも入っている。
全体におだやか、まろやかな手触りで音楽的なスリルはあまり無いように思う。その分、ポップスとしてかっちりとプロダクションされたものが多く、ラストの "Kind Woman" を除くと、イメージほどはカントリー的な要素は感じないなあ。
様々なアイディアを扱いながらつぎはぎではなくひとつのイメージを結ぶように構築した "Questions" と、超ポップな "Merry-Go-Round" が出来としてはひとつ抜けているけれど、個人的には2~5曲目あたりに漂うメランコリックなテイストが物凄く好み。ときにジャジーで都会的、あるいは後期ラヴィン・スプーンフルからフィフス・アヴェニュー・バンドを結ぶ線上にあるようなグリニッジ・ヴィレッジ的なセンス。ボサノヴァの "Pretty Girl Why" なんて実に洒落ているし、"Four Days Gone" はティム・ハーディンのようでもある。
これ以前とは別のグル-プになってしまった感がないではないが、いいアルバムですな。
2018-08-25
エラリー・クイーン「犯罪コーポレーションの冒険 聴取者への挑戦Ⅲ」
エラリー・クイーンによるラジオドラマ脚本集第三弾。9年ぶりに続編が出たというのは、つまりクイーンは今、ちょっと良い感じが来てるのでしょうか。以前の二冊と比較してボリュームがかなり増している。その分、値段も張ります。
肝心の内容なのですが。前二冊にはミステリとして『エラリー・クイーンの冒険』『~新冒険』に通ずるような質があったと思います。正直、今回のはそこまでではないかな。振り返ってみて、おお、巧く作ってあるな、と感心するのであって。仕掛けにあるクイーンらしさを鑑賞する、という類のものだと思う。早く言えばファン向けです。
一方で、プロットには捻ったものが多い。ある程度ルーティンを外していくような展開や意外なタイミングが楽しく、この辺りの魅力は現代でも通用するのではないかと。
印象的だったものをば。
「一本足の男の冒険」 1943年に放送されたもので、戦意高揚のプロパガンダにはいささか辟易してしまう。ミステリとしては密室ものだが、主眼はそこにはない。犯人確定のロジックはシンプルにして、奇妙な状況をすっきりと落とし込んだクイーンならではのテイスト。
「カインの一族の冒険」 3人兄弟のうち遺産を引き継ぐのは一人だけ、その者が亡くなれば他の二人で分けろ――。旧約聖書から引いたであろう名前といい、申し分なくはったりの効いた導入は身内同士での殺し合いを示唆する。しかし、そこからの展開は徹底してオフビート、あれよあれよという間に〈聴取者への挑戦〉へ。
「犯罪コーポレーションの冒険」 強力な誤導を効かせたフーダニット。読み返しが利く書籍だからこそ、その大胆さに感心できるというものだ。当時、放送を聞いていたひとは唖然としたのではないだろうか。
「見えない手掛かりの冒険」 殺人予告を扱っているが、レギュラー・メンバーのほかには被害者しか出てこない、という大向こう受けを狙ったようなパズル・ストーリー。
「放火魔の冒険」 犯人がトリックを仕掛けるタイミングの大胆さ、ただひとつの物証から犯人に辿り着くロジック(ある知識から発するものだが)とも実にクイーンらしい切れを感じさせる。
「殺されることを望んだ男の冒険」 この作品のみシナリオ形式でなく、小説で収録されている(残念ながら小説化は他の作家の手によるものだそうだが)ので、いちばん落ち着いて読める。また、プロット自体がトリッキーで楽しい。
それぞれの出来自体には良し悪しがありますが、まぎれもないクイーン作品で未読のものがあれば、手が出てしまうのはファンの性というもの。巻末にはこれまで単行本にまとめられていないエピソードの紹介があって、これもかなりの労作だと思います。
2018-08-11
Buffalo Springfield / What's That Sound? Complete Albums Collections
バッファロー・スプリングフィールドの3枚のアルバムをミックス違いも独立させて収録した5枚組。セカンド「Buffalo Springfield Again」のモノラル・ミックスは初リイシューになります。一方、ファースト・アルバムの初回プレスにのみ収録され、その後は "For What It's Worth" と差し替えられた "Baby Don't Scold Me" のステレオ・ミックスは今回も入っていません。"Mr. Soul" のシングル・ヴァージョン(ギター・ソロが異なるのだ)といい、もうマスターテープが存在しないのかも。
彼らのボックスセットは2001年に4枚組のものが出ていて、そちらはレアトラック満載のHDCD仕様でした。今回のリリースはHDCDではありませんが、マスタリング自体は更に良くなっているように思います。
パッケージの方は簡素なつくりで、ブックレットも無く、ニール・ヤングのコメントが載った紙が一枚のみ。この辺りはニールのソロ・アルバムのボックス単位でのリイシューに近い形態。
なお、2001年のもの同様、ニール・ヤングはスーパーバイズやなんやらで関わっているのですが、スティーヴン・スティルスはこのリリースについてメディアの取材を受けるまで全く知らされていなかったそうです。
バッファロー・スプリングフィールドは活動期間が二年くらいしかないので、バンドというよりソロ・アーティストの寄り合い世帯みたいなイメージがあるのね。実際、全員揃ってスタジオ入りしたのはファースト・アルバムだけだし。あと、デューイ・マーティンのドラムはヘタクソでレコーディングでは使い物にならなかった、という話もあるが、そこを掘り始めると長くなるので割愛。
「Buffalo Springfield Again」のモノラル・ミックスに関しては好きずき、といったところか。1967年の米国産のアルバムだとたいがいはステレオのほうが出来はいいと思っているのですが、「Again」の場合は編集やオーバーダブの継ぎはぎ感がとても激しいので、まとまりとしてはモノラルのほうが良いかな。
それよりも改めて聴いていて思ったのは、寄せ集めのはずの「Last Time Around」ってこんなに良かったっけ、てことです。2001年ボックスでの扱いが良くなかったのを思うと、色々と考えてしまう。ニール・ヤング史観、とか。
2018-08-04
カーター・ディクスン「九人と死で十人だ」
本来は客船であるエドワーディック号は、戦時下ということでありニューヨークからイギリスへ軍需品を運ぶ任務も担っていた。その途上である女性客の喉が掻き切られる殺人事件が発生、被害者の衣服には犯人のものと思しい血染めの指紋が残されていた。早速、乗船している全員から指紋を採取、照合が行われる。しかし、その結果、一致するものが見つからなかったのだ。勿論、海の上であり外部から船への出入りは不可能だ。犯人はいるはずのない十人目の乗客なのか。
1940年、 ヘンリ・メリヴェール卿もの。
『盲目の理髪師』同様、船上ミステリです。もっとも、『盲目~』がまるっきり喜劇であったのに対して、全体に戦争の影が大きく落ちておりシリアスな雰囲気です。ところどころにふざけたやりとりがあって、いいスパイスにはなっていますが。
ミステリとしては指紋の謎が当初よりもずっと大きなものになっていくのが良いです。まず、化学分析により作り物ではなく実際の人間の指から付けられたものであることが事実として証明される。また、偽装だとしたら、そもそもクローズドサークルでそんなことをする目的が理解できない、となってしまう。しかし、船内に隠れている人間などいないのだ。
そうしているうちにさらなる殺人が起こる。
指紋の謎の解決には正直、拍子抜けの感を受けました。そんなことが出来るのかな、みたいな。しかし、フーダニットとしては非常に良く出来ています。ごくシンプルなトリックが絶妙な演出によって見え難いものになっている。戦時下であることが実にうまく機能しているのも素晴らしい。
分量からして軽量級ですが、すっきりとして切れのある出来栄えです。この時期におけるカーの美点が良くわかる作品ですね。
2018-07-31
エラリー・クイーン「エラリー・クイーンの冒険」
1934年に出版されたクイーンの第一短編集、その新訳。元本の初版にのみあったというJ・J・マックによる序文は今回初訳だそうです。各編の雑誌発表も1933、34年と短期間に集中していて、脂が乗っていたことが伺えます。
全作品、旧訳で何度か読んでいるのですが、簡単な感想をば。
「アフリカ旅商人の冒険」 謎解き短編の教科書的なパターンをなぞったような作品。多重解決が魅力であるが、いかんせん紙幅が少ないので偶然に頼っている面があり、半ば探偵小説のパロディのように感じてしまう。しかし、腕時計をめぐる推理にはちょっとした盲点を突くものがあります。
「首吊りアクロバットの冒険」 一転して読者を引っ掛けることに力を注いだ作品。ブラウン神父譚にヒントを得たようなホワイダニットの趣向もすっきりと決まった。
「一ペニー黒切手の冒険」 シャーロック・ホームズの有名作から来ているような発端からひとひねりしたプロット。さらに解決にも別のホームズ作品を思わせるアイディアがあって楽しい。
「ひげのある女の冒険」 クイーンとしては最初期のダイイング・メッセージもの(細かいことをいうと実際はダイイング、瀕死の状態ではないのだが)。現在から見ると流石にシンプル過ぎるけれど、その一方で犯人、トリック、動機を一度に貫いていく鮮やかさは捨てがたい。また、容疑者たちのキャラクターには後の『Yの悲劇』を思わせるところがある。
「三人の足の悪い男の冒険」 誘拐もの。まあ、これも今となっては、というトリックではあるが、犯人による不注意を装った工作と本当の不注意を並べた皮肉、エラリーが自らの推理に確信を得るタイミングなどからは独自性を感じます。
「見えない恋人の冒険」 後のライツヴィルものを連想させるような舞台設定が楽しい。またもブラウン神父を思わせる後半の展開。しかし、小さな違和からはじまった演繹が遂には唯一の犯人を指し示す推理の流れからは、これぞクイーンと思わせられる。
「チークのたばこ入れの冒険」 スピーディーでツイストのあるプロット、物証からの見事な犯人断定等は国名シリーズを濃縮したような味わい。ただし、咄嗟に行動した犯人の勘があまりに良過ぎる(言い換えればご都合主義)のは否定できない。
「双頭の犬の冒険」 これはホームズ譚から来ているようなプロット、手掛かり。いささか古臭い感は否めない。じっくりとした雰囲気の書き込みこそが見所か。
「ガラスの丸天井付き時計の冒険」 ダイイング・メッセージその2。しかし、既にこの趣向そのものが対象化されている、というのが凄い。また、一見複雑な状況を解き明かすロジックもとても明快だ。
「七匹の黒猫の冒険」 発端の謎はまたしてもチェスタトン的。フーダニットとしては非常にスマートな仕上がりで、誤導も申し分無いと思う(が、動機までは手が回らなかったか)。
「いかれたお茶会の冒険」 ルイス・キャロルをモチーフにした "mad" な状況作りが素晴らしい。これにより、ミステリとしての微妙な描写も可能になっている。ひとつの違和から唯一の容疑者へ導かれるロジックもシンプルで、気持ちの良いものだ。
各々40ページほどの中にひねりのある謎解きとしっかりとした肉付けもなされていて。やはりクイーンの短編集ではこれがベストですね。
次回は『シャム双子の謎』の刊行が予定されていますが、何時なのかは書いてないね。
2018-07-24
Chris Rainbow / White Trails
1979年にリリースされた3枚目のアルバム。最近、英Cherry Red傘下のLemonというところからボーナストラック入りでリイシューされました。
アレンジ、プロデュースはクリス・レインボウ本人。演奏はモー・フォスターやサイモン・フィリップスらセッション・ミュージシャンによるもので、涼やかなエレピはマックス・ミドルトン。また、ギターには元パイロットでアラン・パーソンズ・プロジェクトに参加していたイアン・ベアーンソンの名前がある(クリス・レインボウもこの後、アラン・パーソンズ・プロジェクトのレギュラーになります)。
このアルバム、大昔に聴いて、そんなにいいとは思わなかったのよな。日本のレコード会社の売り文句から、こちらが勝手にビーチ・ボーイズ的なものを期待していたせいなんだけれど。確かにメロディとコーラスにはそういった要素があります。しかし、オケは時代相応のアダルト・コンテンポラリーというかシティ・ポップじゃないか、と。AOR的なものはどうも苦手なのよ。若い頃には特にそうだった。
しかし今、先入観を排して接してみると英国モダンポップ的なセンスがそこここに感じられ、おお、思ってたのよりずっと良いじゃないか、となったわけ。コーラスのエフェクト処理、ギターの音色、ぐねぐねしたフレットレスベースのフレーズ等、当時の典型的なサウンドからは一線を画したものであります。
歌声の方は甘さとシャープさの両面を併せ持ち、カール・ウィルソン的な瞬間もある。また、クロースハーモニーになると、ひとり多重録音で作っているせいかタイミングがジャストで、そのことから密室的な印象を受けます。
"Song Of The Earth" がアコースティックな響きを生かした開放感ある曲で、'70年前後のビーチ・ボーイズを思わせ、個人的に一番好みであります。凝りまくったコーラスアレンジもたまらないわあ。
メロウ化した末期パイロット好きなひとなんかにも合うアルバムじゃないかと。
2018-07-17
The Who / Live At The Fillmore East 1968
50年前の4月6日、ニューヨーク公演の演奏。
当初、ライヴ盤を作るべくこの日とその前日の公演が録音され、それらからピックアップしたアセテート盤も作成されたがお蔵入りに。そのアセテートをソースにしたブートレッグも古くから出回っていました。
今回のリリースは4トラックをレストア、新たにミックスされたものであります(なお、ライナノーツによれば5日のマスターテープは行方知れずだそう)。
音の方は'60年代のライヴということを考えれば、かなりいい。演奏のほうも当時のザ・フーだからいいに決まってら。他にはモンタレー・ポップ・フェスティヴァルくらいしかないわけだし。
とはいっても30分を超える "My Generation" は実は10回あまりしか聴いていない。どうもとりとめが無いようで疲れる。一番いいのが、ロジャー・ダルトリーが "f-f-f-fade away" と歌っている途中でジョン・エントウィッスルが勝手に "fade away!" と叫ぶところだったりする。
このライヴが行われたのはサード・アルバム「Sell Out」の本国でのリリースから4ヵ月も経っていないころ(アメリカだと3ヶ月)で、その「Sell Out」からの曲も演奏しているけれど、ここでは完全にサイケデリックを脱している。バンドとしては既に'70年代以降のモードに移行しているようである。ハアアアド・ロック!
それにしてもフーのサウンドというのは独特だ。そして、ライヴだとさらに硬質でドライな印象を受ける。ベースはトレブル強め。タウンゼントのギターは暴力的でありながら繊細、歪んでいるけれど一音一音はクリアに聞かせる。キース・ムーンについていうと、ドラムキットが大きくなってからは精彩を欠いていった印象を持っているのだが、この時代はまだ手数の多さがグルーヴを邪魔していなくて、いいですなあ。
2018-07-16
三津田信三「碆霊の如き祀るもの」
江戸時代から現代(作中では戦後)にかけて起こったとされる四つの怪異。それを取材すべく刀城言耶は断崖に囲まれた海辺の村へと向かった。しかし、というか、やはり事件が起こる。それは伝え聞く怪談の内容と呼応するようなものだった。
刀城言耶シリーズとしては六年ぶりの新作。
見立てによる連続殺人が起こり、それらがそれぞれに一種の密室であり、なおかつ有力な容疑者も挙げられないという、探偵小説としては王道のような設定であります。
語りのほうはすごくテンポがいい。ひとつひとつのエピソードが短めで、場面展開も早い。県警の警部が捜査の指揮を執るのだが、この人物が言耶の意見を聞きつつ現実的な見地からそれを検討していくというかたちをとっているので、読んでいてストレスがないし、物語途中での推理興味も十分。
一方でじっくりとした描写があまりないので、恐怖という点ではやや物足りないか。
事件のスケールが大きいためにあちらを立てればこちらが、となって中々、真犯人の目処が立てられず。そのまま終盤に至ると、70点にも及ぶ疑問が列挙されていく。
謎解きはスクラップ&ビルドを繰り返し、最終的に視点を変えることで全貌を見通すというもの。モダーン・ディテクティヴ・ストーリー的なロジックの意外性には堪えられないものがあるけれど、細部は先にいったん提示された仮説の中から再構成されていく分、読者の方が一足先に真相に辿り着いてしまうのは仕方がないか。
怪談の謎と現在の事件の絡ませ方といい、ミステリとしての洗練は相当なものになっているのだが、トリック一発の衝撃には欠ける。この辺りは好き嫌いはあるだろうな。
……と思っていたら結末で見事な着地が決まった。そして、あらためて作品の最初に置かれた「はじめに」の部分を見返すとなかなか読後感が深まってくるじゃないですか。
う~ん、わたしは満足です。
ところで、このカバー絵、帯を外してみてどきっとしたな。
2018-07-09
ヘレン・マクロイ「牧神の影」
1944年のノンシリーズ長編。
はじめのうちに暗号が提示されるものの展開としてはスリラー、最後になって謎解きがまとめて押し寄せてくる、といった感じの作品です。
主人公の女性が感じる不安には二つのベクトルがあって。森に棲むように思われる超自然の存在と、素性の胡散臭い人物に代表される現実的な脅威。人が欲望に囚われた末に得体の知れないものになってしまう、というのが作品のテーマのひとつではあるけれど、次元が違うものが混ぜこぜになっているようで、どうにも説得力が薄く感じられてしまった。
サスペンスが中途半端に思えるうえ、具体的な事件が起こるのも終盤、そのうえ暗号も難解とあって、なかなか読み進める気が起きなかったのが正直なところ。マクロイでこんなに苦戦したのは初めてだ。
で、解決編なんですが。
フーダニットとしてはやや緩いし、伏線にも乏しいのではないかな。一方で遠い過去に属する事柄が読み替えられる趣向はさすがマクロイ、といったところであります。
また、暗号そのものはともかく、鍵となるものとそこへ辿り着くロジックも好みですね。
丁寧に作られた作品ですが、どうも個々の要素が有機的に絡んでいないようで、すっきりとしないな(暗号小説であることそのものがフーダニットにおける誤導として生きていればよかったのだけれど)。個人的に今回はあまり合わなかったですね。
八月に出る『悪意の夜』に期待しましょう。
2018-06-10
ジョン・ディクスン・カー「盲目の理髪師」
1934年長編、その新訳版。
これ読んだことあったっけ? と思っていたのだが、なんとなく既視感を覚えるシーンや設定がある(しかし自信はない)。
ユーモアの要素が大きい作品ですが、船上ミステリであり安楽椅子探偵ものでもある。旅客船で起こった事件の関係者がフェル博士の自宅を訪ね、自分の見聞きしたあらましを博士に伝える。そして、そこからフェル博士が真相を推理する、という構成。フェル博士は物語のはじめと真ん中、それに解決編のみに顔を出す。
ミステリとしての主題は盗難の犯人と消えた死体の行方、なのだが、それらがどう関連するのかという全体像はなかなか見通し難い。
もっとも、お話は必ずしも謎を中心に進行しているわけではなく、繰り広げられるドタバタの描写に多くの頁が割かれております。登場人物たちがそれぞれ勝手な思いつきで動くので、良くも悪くも話の先行きが見えない。そのせいで、問題の焦点がぼやけている感はありますね。もはや真相などどうだっていいや、というような。
で、そのドタバタなのですが、現代の日本人からするとどうかな、といったものですね。個人的には笑えるところはいくつかあったものの、全体としては夾雑物過多というか、間延びしているような印象を持ちました。
謎解きとしてはゆるめです。伏線は大量に回収されていくけれど、決定的な証拠は無いように思える。また、捜査が不十分で穴があった、というのもなんとも。
一方で、アクシデントを誤導につなげ、さらにそれが大きな手掛かりにもなる、という趣向は実にうまいし、非常に大胆な描写がなされていたことがわかるところなど、たまらないのだけれど。
あくまで喜劇がメインかな。
次は『九人と死で十人だ』ですね。
2018-05-26
福永武彦「完全犯罪 加田伶太郎全集」
福永武彦が加田伶太郎名義で発表した探偵小説集、その創元推理文庫版。
大学助教授である伊丹秀典が探偵役を務めるもので、1956~62年に発表された8短編が年代順に収録されています。なお、加田名義では他にノンシリーズでふたつほど短いものがあるのですが、それらはこの創元版では除かれています。
「完全犯罪」 未解決に終わった事件の話を聞いた複数の人物たちが、それぞれの見解を披露するというもので、フーダニットと密室の謎を絡めたガチガチの謎解き小説。相当に古典的なスタイルであって、相当無理目のトリックはあそこから来ているのかな、と見当も付くもの。それでもアイディアの密度が高い、力のこもった作品ではあります。
「幽霊事件」 屋敷の一室で死体が目撃された直後、その被害者当人が頭から血を流しながら玄関から入ってくるという不可解極まりない謎。密室の要素もある。
書かれた時代からしても古めかしいし、あまりに犯人の思い通りに行き過ぎているのがなんですが、相当にトリッキーだ。
「温室事件」 またしても密室殺人である。しかし、現場の特性を生かしたトリックや細かい伏線等、ミステリとしての練度は上がっているし、物語性への配慮もしっかりしたもの。それでいてアマチュアリズムも感じられるというのが、また嬉しいところ。
「失踪事件」 わずかな手掛かりから隠れた犯罪をあぶりだすという趣向で、展開されるのは推理というよりは想像に近いですが、ちょっとハリイ・ケメルマンの有名短編を思わせます。
「電話事件」 PTA会長のもとに脅迫電話がかかってくる。しかし、要求は何もしてこない。不可解な謎を解くべく、伊丹助教授は自ら学校関係者たちへの聞き込みにあたるのだが、容疑者たちには皆、犯人とするにはしっくりこないところがある。
私立探偵小説を思わせるプロットで、推理の妙にはやや乏しいか。
「眠りの誘惑」 ある屋敷に雇われた女性の手記からなる一編で、伊丹英典本人は顔を出さず、最後に手紙でその推理を述べるというもの。安楽椅子探偵の形式を極端にしたといえるか。
犯行手段は相当に無理があるものと思われるのだが、ロジックの切れはこれがベストではないかな。全体の雰囲気や余韻も決まって、とてもまとまりのいい作品です。
「湖畔事件」 子供たちが活躍する殺人喜劇で、必ずしも謎解きに主眼は無いように思える。入り組んだプロットだがうまくまとまっていて、楽しい読み物になっています。
「赤い靴」 自殺したと思われる女優が残した日記には、彼女が日常的な怪異に悩まされていたことが記され、さらにそこから殺人の可能性も浮かび上がってくる、というもの。
怪奇的で不可解な現象と謎解きの興味を結びつけ、シリーズ最終作にふさわしく読み応えある作品です。
いずれも力を抜いたものがなく、趣味性を感じさせる仕上がりです。謎解きの興味を中心に据えながら、6年のスパンの間に作風がドラスティックに変化していくのも興味深い。
しかし、巻末に掲載された鼎談における都筑道夫の論はやや牽強付会のきらいがありますね。
2018-05-19
Revelation / Revelation (eponymous title)
リヴェレイションという名の詳細がわからない混声ボーカルグループによる、1969年か'70年にマーキュリーから出されたアルバム。ジャケット裏には「THE MUSIC OF JIM WEBB IN A NEW SETTING BY REVELATION」とあり、収録曲は全てジミー・ウェッブの作品で固められています。
プロデュースはブラッド・ミラーという、オーディオファィル御用達であるモービル・フィデリティ・レコーズの創立者が、アレンジにはリチャード・クレメンツがクレジットされています。ブラッド・ミラーはイージー・リスニングにSEを混ぜたレコードをヒットさせていたひとですが、どうも自身にはさほどの音楽的な素養はなかったよう。クレメンツのほうはバッキンガムズのアレンジに参加したりしていて、'70年前後にはミラーとともに数枚のレコードを制作しているようであります。
録音はロンドンとサンフランシコのスタジオが記されていて、おそらくオケを英国で作り、歌入れや少々のSEを入れるのを米国で行ったのではないか、と推測されます。想像ばっかりですが。
収録されている12曲は最初に触れたように全てジミー・ウェッブの作品ですが、ここが初出かと思われるものが3曲ほどあります(リリース時期が確定できないのですが、もしかしたら5曲かも)。他にはテルマ・ヒューストンのアルバム「Sunshower」(1969年)にも入っていたものが4曲ありますが、仕上がりからはかなり異なった印象を受けます。
このアルバムと違い、ジミー・ウェッブが作曲だけでなく全面的に制作に関わったアルバムには割合によく知られたものがあります。先に触れたテルマ・ヒューストンの他にジョニー・リヴァース、リチャード・ハリス、フィフィス・ディメンション等々。それらと比較すると、このリヴェレイションの歌やコーラスは美麗ではありますが、個性や存在感はそれほど感じないのです。というか、主役はシンガーではなくて曲のほうだ、というつくりではないかな。じっくりと聞かせるよりも、軽快さのほうが勝っている、とも言えそう。
当然のように良い曲ばかり、それらをソフトサウンディングに仕上げたアルバムなわけなので、単純に聴いていて気持ち良いですね。
似た趣向であるレヴェルズの「The Jimmy Webb Songbook」もどこかでリイシューしてくれないかしら。
2018-05-13
Chris Bell / I Am The Cosmos
「I Am The Cosmos」、その決定盤としたい2CD。昨年に米Omnivoreからリリースされたものです。
クリス・ベルはビッグ・スター脱退後、その生前にはシングル一枚しかリリースしていません。アルバム一枚分のマテリアルは制作してあったものの、レコード会社の十分な関心を得るに至らなかったのだ。1992年になってライコディスクがそれらを纏め上げたのが「I Am The Cosmos」というタイトルのCDであります。そして2009年にこのアルバムのデラックス・エディションがライノ・ハンドメイドからリリースされた際には、ライコ版から曲順が少し変更されていました。Omnivoreからのものは、さらに未発表のものが追加されていますが、アルバム部分についてはライノ・ハンドメイド版の曲順を踏襲してあります。
このアルバム、半数近くの曲ではビッグ・スターのメンバーが演奏に参加していますし、クレジットされていないもののアレックス・チルトンとの共作曲もあります(ビッグ・スターから脱退する際、チルトンとベルの間で共作曲はそれぞれが分け合うという話し合いがされていたそう)。実際、初期ビッグ・スターの延長ですから、いいに決まっています。しかし、全体とするとサウンドの抜けがいまひとつな感じも受けるのだなあ。
レコーディングは地元メンフィスとフランスで行われ、後にジェフ・エメリックのもと、ロンドンのエアー・スタジオでオーバー・ダブとミックス。そして、さらにその後メンフィスで色々と手直しがなされたそう。で、思うに曲によってはスタジオワーク好きのベルがいじり過ぎたのではないかな。エコーを深くしたのはジェフ・エメリックのセンスらしいのですが。
アウトテイクや別ミックスの数々を聴いていると、演奏の表情が生き生きと伝わってくるようで、パワーポップとしてはこっちのが格好良いのが多いな。
それでも、タイトルになっている "I Am The Cosmos" は(4ヴァージョン収録されているのだけれど)シングル・リリースされたものが一番ですね。幾重にもオーバー・ダブされたギターが共鳴、干渉しながら絡み合って形成されている音の層は独特の美しさ。メランコリックな曲調もテープスピードを上げることで(これはレーベル・オーナーであったクリス・ステイミーのアドヴァイスだそう)、ちょうどいい塩梅のものになっているのだと思います。
2018-05-01
Ranny Sinclair / Another Autumn
ラニー・シンクレアという女性シンガーが1960年代中期、Columbiaに残した音源集。昨年にSundazed傘下のModern Harmonicというところから出されたものです。
全4枚のシングル両面に未発表であった4曲を加えた全12曲がモノラルで収録されており、マスタリングはボブ・アーウィンが担当。
当時のレコード制作はテオ・マセロによるもので、ジャズ色を感じさせるポップス。そこにウィスパーボイスに近いようなソフトなボーカルが乗っかっています。
曲はミディアムとスロウが半々。スロウの曲は割合にコンテンポラリーなポップスに近い感触のものが多いのですが、テンポ速めの曲におけるジャズとポップのバランスが絶妙です。
中では一曲目の "Fan The Flame" が一番良いな。スパイ映画を思わせるようなブラスが効いたスリリングで華麗な曲調が一転、クールなフォービートに変化する展開が格好いい。
他にも、高速ジャズワルツの "Wailing Waltz" は渋く決まっているし、サンシヤインポップ的な要素が強い "Bye Bye" などはインナー・ダイアローグあたりを思わせるスマートな出来栄え。
また、未発表曲でも軽快にスイングする "There Won't Be A Trumpet"、"A Wonderful Guy" など、実に洒落た仕上がりです。
ポップスとしては装飾控えめなアレンジと甘い歌声がちょうどいい具合であって。あえて近いものを挙げるとしたらブロッサム・ディアリーになるかな。
2018-04-30
S・S・ヴァン・ダイン「カナリア殺人事件」
新訳ヴァン・ダイン全集、その二巻目ですが前作の『ベンスン殺人事件』より5年経っているのね。凄く悠々としたペースであります、さすが古典。
この『カナリア~』には大きなトリックが二つあるのだけれど、昭和の時代には色んなところで言及されていまして、それもあまり良い扱いじゃないほうで。まあ、それだけわが国でかつては影響力があった、ということでもあります。
それはともかく。前作『ベンスン~』と同じく凄く気合が入った読み物ですね。だれ場もない。『ベンスン~』と比べるとプロットに中盤の捻りが加わり、事件の複雑性も増しています。ファイロ・ヴァンスのキャラクターもより厭味でいい感じです。
その一方で、手掛かりや伏線の出し方は下手ですね。トリックの解決などまったく唐突です(ヴァンスは霊感が降りてきた、とかなんとか言っていますが)。また、真犯人も今の目からするとバレバレ。
読みどころはやはり雰囲気になりますか。なんだろうな、この迫力は。パイオニアである自負からくるのか、オリジナルの強さなのか。
ポーカーを通じて容疑者の性格を分析する趣向など、当時はそれなりに自信のあるアイディアではあったのでしょう。実にはったりが利いていて楽しいです。
まあ、はっきりいってマニアかおっさん向けであって若い人には勧めませんが、個人的には面白く読めました。
次はいよいよ『グリーン家殺人事件』ですな。どれだけかかってもいいのでせめてシリーズ前半の6冊は出していただきたいものです。
2018-04-21
パーシヴァル・ワイルド「探偵術教えます」
お金持ちのお抱え運転手、ピーター・モーランは勘は悪いが人当たり良く、若い女の娘にめっぽう弱い。もっか通信教育で探偵術を学んでいるのだが、生かじりの知識を実地に試しているうちにさまざまな犯罪に巻き込まれてしまう。そして、まるっきり事態を把握せず、勘違いしたまま行動しているうちに何故か事件を解決に導いてしまう。
1940年代後半にEQMMを中心に発表された短編をまとめた連作集。単行本収録の7作品に、後に書かれた1作を加えたシリーズ完全版になっています。
収録作品中、最初の「P・モーランの尾行術」がユーモア・ミステリとしては一番良かった。すれ違いのシチュエイション・コメディとして良く出来ているし、スラップスティックとしても出色。ピーターが最初から最後までずっととぼけた調子なのもいい。
そのあとのいくつかは面白いけれどプロットのパターンが同じなので、一話完結型の連続ドラマを見ているようだ。なんとなく怪しい人物はいるけれど明確な謎があるわけではないこれらには、探偵行為はあっても推理の妙には乏しいので、より純粋なユーモア小説としてのテイストが強い。
それが後半になってくると、事件を解決してきた実績を買われて、ピーターのもとにちょっとした問題が持ち込まれるようになる。そして、ピーターがお手上げになってしまった事件の話を聞いて、他の人間が解決してしまう、というパターンが生まれる。それほどかちっとした謎解きではないが、伏線もちゃんとある。
そんな中では「P・モーランと消えたダイヤモンド」が、大学で探偵小説を学んだという女の子が活躍して、ジャンルのパロディとしての面が全開。ピーターの暴れっぷりも実に楽しい。また、単行本では最後にあった「P・モーラン、指紋の専門家」ではシリーズを締めくくるのにふさわしい、ちょっとした捻りがあって、これには思わずにやりとさせられる。
何より肩が凝らず、楽しく読める一冊でありました。
2018-04-11
麻耶雄嵩「友達以上探偵未満」
女子高生コンビが探偵役を務める中編三つを収録。
パッケージには不安になってしまったが、中身はガチガチのパズラーでありました。
「伊賀の里殺人事件」
三重県伊賀市で行われるミステリーツアーに放送部の取材で訪れた伊賀ももと上野あおが殺人事件に遭遇する。
舞台を別にすれば事件そのものはそれほど変わったところが無いように見えたのだが、警察の捜査が進むうちに予想外のものが発見され、様相が混沌としていく。方程式の変数がいきなりひとつ増えた感じです。
終盤になって読者への挑戦らしきものが登場しますが、本質的にはモダーン・ディテクティヴ・ストーリイであって、パズルとして考えると難度は非常に高い。作中でも説明されているように二人一役と一人二役が交錯することで表面的な辻褄が合っていたのに、更にその延長上で盗まれた衣装と堀の底から発見された衣装の二人一役が起こってしまう、という趣向が何気に凄い。
「夢うつつ殺人事件」
美術部に所属する女生徒が部室の裏で居眠りをしているときに、ある男女カップルが美術部の先輩を殺そうという相談をしているのを耳にしてしまう。
トリックの実現性が難といえばそうですが、これはちょっと見たことのない仕掛けではあります。読者に向けた叙述トリックをそのまま作品内のキャラクターたちにも作用させてしまう、というか。更には読者、探偵だけでなく犯人までがトリックに引っかかり、その結果として殺意が生まれるタイミングも実に意外なものであって。いや、大した作品です。
「夏の合宿殺人事件」
あおとももが中学生の時に遭遇した事件。
二人の探偵の関係を裏から明かすもので、同じ作者の木更津悠也ものを思わせるところがあります。また、この作品には読者への挑戦がないのだが、他の二編でのそれがあおは既に謎を解いたと思わせる一種のミスリードであった、というのに唸りました。
純粋にパズラーとしても一転・二転する推理が楽しめます。
うん、手触りは軽いけれど、期待を裏切らない出来ですね。
2018-04-08
Bradford / Thirty Years Of Shouting Quietly
ドイツのA Turntable Friendというところから出た二枚組。
タイトルからしてアルバム「Shouting Quietly」、その30周年記念かと思ったのだが、良く考えると「Shouting~」がリリースされたのは1990年だから未だだな。ブラッドフォードがインディー・レーベルより初めてシングルをリリースしたのが1988年なので、そこから30年ということか。
ディスク1はアルバム「Shouting~」のリマスターとシングル曲が4曲。今回のものでファウンデイション・レーベルでの曲が全部揃えばいいな、と思っていたのだが、シングルのカップリングで漏れているものがあるようで残念。
ディスク2は1曲目がシングルB面であった "Tattered, Tangled And Torn"。
続いての8曲には(ファウンデイションのオーナーでプロデューサーの)スティーヴン・ストリートが立ち会ったプリプロから最終的にはアルバムには入らなかった4曲と、それ以外のデモが混じっています。うち、後者がちょっとややこしい。聴いた感じ、2曲は1988年にフランスのみでリリースされたミニ・アルバムに入っているのと同じテイクに思えます。"Saturday Insanity" も同じに聴こえるのだが記載されている録音スタジオは違う。また、"Laughing Larry's" はインディーでのデビュー・シングルと同じスタジオが使用されているので、同時に録音されていたものかも。
まあ、細かい話は置いておくと、アルバムに採用されなかった曲は純粋に楽曲としての出来の差だと思うのですが、もろスミス・フォロワーというようなギターが聴けるものもありますね。
次の4曲はアルバム後に制作されたデモ。サウンドがハード目になっていたり、インディーダンス的なリズムのニュアンスの曲もあったり。悪くもないけれどうたの表情が埋もれてしまっているようであって。スティーヴン・ストリートはこの辺りのバランスがうまかったのだろうな。
最後は "Gang Of One" のリミックスと "Skin Storm" のオリジナル・シングル・ヴァージョン。"Skin Storm" は再演版と比べると演奏に粗さを感じますが、はじまりの瑞々しさが素晴らしい。
2018-03-21
The Ronettes / Everything You Wanted To Know About The Ronettes …But Were Afraid To Ask
今年の初めに出たロネッツのコンピレイション。「everything you wanted know about ~ but were afraid to ask」で「いまさら聞けない~についてのすべて」くらいの意味ですね。
このCDは大手通販ショップで扱っているし、帯・解説を付けた国内盤も出ていますが、使用音源の権利関係についての記載がないのでブートレグでしょう。作曲クレジットもありません。
全27曲のうち、ステレオミックスが9曲、未発表曲が3曲含まれております。ステレオは「Presenting Fabulous Ronettes Featuring Veronica」収録曲からのもので、充分聴ける音になってます。しかし、並びで(おそらく正規盤をソースにしたであろう)モノラル曲が入っているので、それと比べるとやはり劣る感じはするな。
さて、今回の目玉である未発表曲ですが。"Padre" はヴェロニカのソロボーカルによるもの。やや地味な曲ですが音質は非常にいいです。"Close Your Eyes" はしっかりとしたプロダクションで、ちゃんと当時のロネッツの曲になっています。音質もまあ悪くない。残る一曲の "Someday" はデモでしょうか。テープがだいぶ痛んでいるようで、音がよれよれ。楽曲自体はキャッチーなフックがある軽快なものなので、最後まで仕上げられていないのが残念です。
他は全て既発表曲なのですが、グループ解散後にさまざまな編集盤で日の目を見たものが網羅されているようで、中でも「Back To Mono」ボックスからも漏れていた "(Baby Let's Be) Lovers" が入っているのが気が利いていますね。
所詮は寄せ集め盤には違いないけれど、往時のロネッツ、その未発表曲となると食指が動いてしまいます。フィレスに関しては過去にブートレグでセッションテープが流出しているので、まだ何か残っていてもおかしくは無いとは思うのですが、Abckoの仕事ぶりからするとオフィシャルのかたちではあまり期待できないかな。
2018-03-19
ロス・マクドナルド「象牙色の嘲笑〔新訳版〕」
1952年の長編、新訳版で再読。二年前に買ってはいたのだが、ずっと放置していました。
はたちくらいのころに一番入れ込んでいた作家がマクドナルドとフィリップ・K・ディックなのだけれどね。歳を取ってからは辛気臭いものはあまり読みたくなくなってしまったのだ。
この『象牙色の嘲笑』はリュー・アーチャーものとしては4番目の長編で、シリーズとしては初期のものとなります。アーチャーがまだまだ若く、感情をはっきり示していて、後の観察者でも紙のように薄い存在でもありません。立場の弱いものには肩入れし、警官に対して反抗的な口をきいたり、自分につかみかかってきた若者を軽くあしらってみせたりします。あと、ちょっとモテたりもする。
筋立てのほうは胡散臭い依頼者からの人探しがやがて殺人事件に結びついて、というもので、捜査が進むにつれて事件の規模が広がり複雑さを増していく。
後ろ暗いものを抱えた人々によるそれぞれの思惑が絡み合った事件。それが、ある瞬間にひとりの人物の行為に収束していく真相はミステリとして素晴らしくかたちがいい。また、一度捨てた可能性が再び浮かび上がってくる仕掛けと、それを成立させるためのキャラクター造りがとてもうまい。
チャンドラーの影響はまだ明らかであって、マクドナルドならではの個性はそれほど感じられないものの、複雑なプロット構成のうまさは既に完成の域にあると思いましたよ。
2018-03-17
Wynder K. Frog / Shook, Shimmy And Shake: The Complete Recordings 1966-1970
オルガン・インスト・コンボ、ワインダー・K・フロッグがアイランド・レコードに残した音源集3CD、英rpmからのリリース。
三枚のアルバムのうちファーストとサードは素性の怪しいところからリイシューされていましたが、オフィシャルなかたちで初めてのCD化となります。さらにシングル曲、宣伝用ソノシートからの曲、BBCセッション、そして未発表アルバムの曲まで入った大盤振る舞いのセットです。
なお、ワインダー・K・フロッグというのは元々バンド名だったわけですが、それがいつのまにか鍵盤奏者、ミック・ウィーヴァーの芸名になっていったそうであります。
「Sunshine Super Frog」(1966年)はウィーヴァーがセッション・ミュージシャンたちと共に制作したファースト・アルバム。
スリーヴノーツにはプロデューサーがジミー・ミラーで、いくつかの曲ではニューヨークで制作したバッキングトラックにロンドンでオルガンをオーヴァーダブした、と書かれていました。ところが、盤自体にはアイランド・レーベルのボス、クリス・ブラックウェルがプロデューサーだと表記されていたのです。今回のライナーノーツを読むと実際にはブラックウェル、ミラー、そして当時レーベルのアレンジャーであったシド・デイルがそれぞれに制作したものより構成されているそう(ミック・ウィーヴァーによれば、レコーディングにはジョン・ポール・ジョーンズが参加していたとのこと)。そのためか(基本線はブッカーT&MG'sあたりだとは思うのですが)ソウル色の強いもの、当時のヒットソングのカヴァー、ストリングス入りのムーディな曲が混在。いずれもウィーヴァーのハモンドはご機嫌なものの、一枚のアルバムとしてはややまとまりには欠ける印象です。
また、マテリアルとしては当時のアイランドらしくジャッキー・エドワーズの曲が3曲取り上げられていて、そのうちひとつはスペンサー・デイヴィス・グループがヒットさせた "Somebody Help Me" であります(さらに翌年にはシングルで "I'm A Man" もリリースしています)。
ファースト・アルバムのしばらく後にウィーヴァーはグループの他のメンバーと袂を分かつことになります。そして、以後のライヴを共にしてきたプレイヤーたちとともに作られたのがセカンド「Out Of The Flying Pan」(1968年)で、こちらはガス・ダッジョンがプロデュース。サウンドの感触がぐっとシャープで、タイトなものになっています。
全体にファンキーな要素を強めつつジャジーな要素も加わって、モホークスあたりと張り合っても遜色のない格好良さ。いかにもモッズ受けしそうなダンスナンバーが多くて、三枚のアルバムのうちでは一番好みですね。楽曲は引き続きカヴァーが中心ですが、ウィーヴァー自身による2曲のオリジナルにおける洗練はなかなかのもの。また、このアルバムでは鍵盤は勿論いいですが、いくつか実にセンス良いギターも聴くこともできます。
「Out Of~」リリース後、しばらくは活動が順調にいっていたのですが、メンバーたちに他のところから大きな仕事の声がかかり、ミック・ウィーヴァー自身も他所のバンドに参加することで、グループとしてのワインダー・K・フロッグの活動は停止。ウィーヴァーはもう自分のグループを率いていくことに興味が無くなってしまいます。
それでも三枚目にして最後のアルバムが1969年に制作され、翌年に「Into The Fire」として米国のみで発売されました(「out of the frying pan, into the fire」というイディオムで「一難去ってまた一難」の意だそう)。楽曲のほうはオリジナルが多くを占めるようになっているのですが、純然たるジャズファンク、鍵盤が入っておらずブルースハープが主役のもの、南部ソウル色濃いボーカル入りのスロウ、まるっきりジミー・マグリフのような渋いオルガンジャズなど多様なものがあって、もう商売抜きでモッズ的な趣味を突き詰めたというところでしょうか。一方では、ラフなギターが入っているのも特徴であって、これまでになくロックバンド的なテイストも感じられる瞬間も。
さて、今回のリリースには'68年、「Out Of The Frying Pan」より前に制作されながらも、これまで未発表であったアルバムが収録されております。ソースはアセテート起しだそうですが、充分に聴ける音にはなっています。
プロデュースはマフ・ウィンウッドで、管楽器があまり使われておらずソウルっぽい装飾は控えめ。バンドらしいというか比較的エッジの効いたサウンドで、当時のクラブでのライヴはこんな感じだったのかな、と思わせる熱のこもった演奏です。また、いくつかの曲でのひとつのリフを執拗に繰り返すような展開は、後々のファンク化への方向性を感じさせるもの。
「Out Of~」との収録曲のダブりは二曲だけであって、ひとつの独立した作品としてもそこそこ良いのではないかしら。
流行に対応しながらも一環してセンスの良さが感じられる、ハモンド好きには堪えられない3枚組でありますね。
登録:
投稿 (Atom)