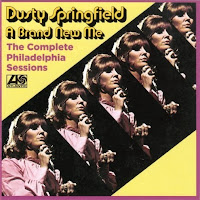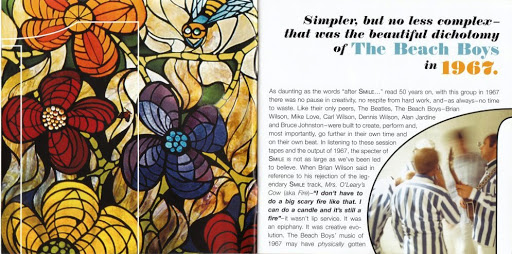2017-12-24
レイモンド・チャンドラー「水底の女」
1943年に発表された長編の、村上春樹による新訳。
旧訳『湖中の女』で何度か読んでいるはずだが、あまり内容を覚えていなかった。今回読み返して気付いたのだが、あまり魅力的なキャラクターがいないのだな。保安官のパットンくらいで。
まあ、そうはいってもチャンドラーなので、その文章を読んでいるだけでも気持ちが良い。死体を発見する場面での、周辺から徐々に核心へ近付いていくような描写はいかにもチャンドラーらしくて嬉しくなってしまう。
この作品で特徴的なのは、フィリップ・マーロウが異様なくらい冷静で、かつ誰にも肩入れせず、誰も恨まないということ。そのために、よりハードボイルド的な要素が強く感じられるものになっているのではないかな。
また、戦時中であることが物語の端々に影を落としている。訳者あとがきではいくつかのディテイルに触れられていて、中でもダムに歩哨が配されていることについての説明にはなるほど、と納得できました。
ミステリとして読むと、チャンドラーがよく使う仕掛けがここではいささか見え易いきらいがある。
その一方、大団円ではマーロウが関係者たちを前にして謎解きを開陳する、そのプレゼンテーションがドラマティックで読み応えがある。特に、殺人の動機が明かされることで、ある人物のアイデンティティが鮮やかに浮き上がってくるくだりは絶品。
さらに、それに続くまるで西部劇のような展開もまた愉しい。
ところで、古い小説を読む楽しみのひとつとしてその時代の空気が再現されることがあると思う。チャンドラーは風俗、ファッション、あるいは建築や内装、家具などを描写することで状況を現前せしめることができた。しかし、あまりに年数が経ち、読者の予備知識も無いとそれらを想像することはだんだんと難しくなってくるだろう。また、翻訳においても訳者が古いアメリカ文化を理解していないと正確なものは為し得ないわけであって。現在よりさらに後年になってチャンドラー作品を訳するひとが出てきたとしたら、そういった部分での苦労は大きくなるのではないかしら。
ともあれ、心地良い読書の時間を過ごすことが出来ました。チャンドラーと訳者に感謝。
2017-12-19
Pugwash / Silverlake
パグウォッシュの二年ぶりになる新作。今月に入ってからはこの一枚だけをずっと聴いていました。
グループからはトーマス・ウォルシュ以外のメンバーは皆抜け、実質的にはトーマスのソロ・プロジェクトとなっています。また、今作のプロデューサー及び録音はジェイソン・フォークナーが担当していて、アコースティック・ギター以外の演奏の殆どもジェイソンがやっているそう。
しかし、先行リリースされ、オープナーでもある "The Perfect Summer" はアルバム中ではむしろ地味というか個性に乏しい出来であって。初めて聴いたときには、あまり芸が感じられないイントロに一瞬、買って失敗したかな、と思ったのだけれど。曲そのものはキラキラした素敵なギターポップで安心、安心。
アルバム全体としてはこれまでと比較してカジュアルでコンパクトになったかと。いかにもUKポップらしい匂いは薄れ、より開放的な印象を受けます。サウンドにおけるギターの比重が高くなり、ストリングスが使われているのはわずか一曲のみ。
バンドという形態に縛られなくなったせいかどうかはわかりませんが、手の込んだアレンジや構成が減り、メロディをしっかり聴かせるほうへ重心を移しているような。これまでになく歌心を響かせる "Better Than Nothing At All" などはロン・セクスミスのようだ(しかし、間奏になると'70年代のウイングスを思わせる展開で、一筋縄ではいかない)。
'60年代っぽい意匠は目立たなくなっているものの、 "Everyone Knows That You're Mine" で聴けるジャングリーな12弦ギターがもろバーズだったり(コーラスでは一転してぐっ、とメロウになるのだけれど)、"Such A Shame" では後期ビートルズ的なアレンジが顔を出したり。大体、いつもベースラインの動かし方がビートルズっぽいんだよなあ。
また、前述したように今作ではギターの活躍が目立つのですが、特にジェイソン・フォークナーの貢献と思えるのが "Why Do I" と "Easier Done Than Said"。前者におけるリズミックな複数のギターの絡みは中期XTCのようだし、"Easier~" でのドライで勢いのあるギターもこれまでのパグウォッシュにはなかったアメリカっぽいテイストです。
相変わらずカラフルで良いメロディ揃いのアルバムでありますが、もう以前とは違うものになった、という感もありますね。マニア受けは要らない、というか。
2017-12-14
アルフレッド・ベスター「イヴのいないアダム」
日本独自に編まれた『願い星、叶い星』に初訳となる2作品を加えた短編集です。
収録全十編のうち1940年代初めに発表された作品がふたつ、1963年がひとつ、残りは全て'50年代に発表されたものとなっています。
「ごきげん目盛り」 アンドロイドとサイコパスを掛け合わせながら抽象的にならず、安っぽくも無い、迫力あるドラマになっているのが凄い。熱に浮かされたような文章のテンポが素晴らしいし、説明を大胆に削りながら物語を成立させられるというのはやはりうまいのだな。これが個人的なベスト。
「ジェットコースター」 歪んだ欲望が疾駆するクライムフィクションで、切れを感じさせる文体が気持ち良い。
「願い星、叶い星」 フレドリック・ブラウンを思わせるプロットの佳品だけれど、説明的になってしまう結末は現代からするとやや締まりがないか。
「イヴのいないアダム」 終末テーマの作品。変わり果ててしまった地球と、もがきながらもはや存在しない海を目指す男、そのじっくりとした描写が読みどころであります。
「選り好みなし」 割合にオーソドックスなSFで、ユーモアの利かせ方がうまい。しかし結末の付け方はいささかくどいように思う。この作品や「願い星、叶い星」を見ると、意外な幕切れの演出はあまり得意ではなかったのかな、と思う。
「昔を今になすよしもがな」 地球上で最後に生き残った男女の物語だが、発端から結末までまるっきりオフビート。荒廃した都市とたがが外れたようなキャラクターの対比もなんだか面白い。
「時と三番街と」 こういう具体的な落ちに向かって組み立てられているものは、今読むと(意味はわかるけれど)あまりピンとこないな。
「地獄は永遠に」 本書の中では一番分量のある中編。それぞれ様相の大きく異なる5つの世界を描き、最後にはそれらがひとつに貫かれるグロテスクなファンタジー。
また、今回追加された「旅の日記」と「くたばりぞこない」は両方ともごく短い作品だが、落ちに頼らないゆとりのある語り口が好ましい。まあ、出来のほうはそこそこ。
同じようなテーマが何度も顔を出すのだが、その料理の仕方はさまざま。何を書くか、ではなくいかに書くか、の面白さですね。
2017-12-07
フィリップ・K・ディック「シミュラクラ〔新訳版〕」
21世紀半ば、世界はヨーロッパ・アメリカ合衆国(USEA)と共産圏に二分されていた。USEAでは巨大製薬メーガーが政府と結託し、精神分析医療を禁止する法案が成立。その朝、精神分析医のスパーブは覚悟の上でいつもと同じようにオフィスに出向き、患者を受け入れた時点で逮捕、連行される。そして、ある人物から条件付で、国中でスパーブひとりだけに医療行為を許可しようという申し出がなされるのだが。
1964年長編。
管理社会下で人々がなんとかマシな生活を送るべく汲々とする一方、一部の特権階級が陰謀を巡らす、そんなお話ですが。
登場人物がやたら多いです。特定の主人公がいない、群像劇というやつですね。仕掛けもたくさんあって、模造人間(シミュラクラ)、タイムトリップ、何十年も全く歳を取らないように見える大統領夫人、念動力で演奏するピアニスト、突然変異の種族、ヘルマン・ゲーリングなどなど。その他、ガジェットも散りばめられ、これぞディックだなあと嬉しくなる。
物語としてはテンポ良く場面が切り替わっていき、その都度新しい展開が生じていくので、読んでいる間はまったく退屈することはありません。後半に入るとそれが加速して、予想もしないような方向へ向かっていきます。
一方で、重要に見えた登場人物が中途で退場して二度と戻ってこなかったりと、色んな要素が投げっ放しで小説としてはまったく収拾が付いていません。
そして、結末は凄く古典的なもの。問題を残しつつ、とりあえずは終わるというかたちで着地します。ある種のSFってこういう締めが許されるのよなあ。
ここ最近の早川からの新訳のうちでは面白い部類の作品だと思います。ディックならではのセンスが暴走していて、実に楽しい読書でした。
2017-12-03
クリストファー・プリースト「隣接界」
近未来の英国、グレート・ブリテン・イスラム共和国は戦争下にあった。中年のカメラマン、ティボー・タラントは長期滞在先のトルコで、爆撃によって妻メラニーを亡くし、政府の手で帰国させられていた。妻の両親のもとで数日過ごした後、政府への報告をするため移動させられるのだが、その道中で見聞きすることから、英国内の様子がまるで様変わりしていることを思い知らされることとなる。また、彼が愛用する量子テクノロジーを利用したカメラは、人体に影響があるため現在は使用が禁止されていることを伝えられる。
章が変わると、時代は第二次大戦中に移る。語り手は奇術師のトム・トレント。彼は自身の持つ特殊な知識や技能を見込まれ、少佐扱いで海軍に呼び寄せられていた。
クリストファー・プリーストの2013年に発表された長編です。二段組で580ページほどありますが、読んでいてそれほど量は感じません。しかし、内容は相変わらず歯応えがありますね。
今作で特徴的なのは虚構性というかメタ趣向が希薄なところでしょう。これ以前の長編では、それが誰かの手に拠って書かれた文章であることが明示されていて、その信憑性には疑いを挟む余地があったのですが。この作品の少なくとも近未来のパートは三人称、神の視点から書かれており、従ってどれほど辻褄が合わなくとも、それを事実として受け入れて読み進めることになります。このおかげで、プリーストの作品として『隣接界』はかなり判りやすいものになっていると思います。
とはいっても、あくまで能動的な読書態度が求められる辺りはいつも通り。作中で謎が立ち昇り、その回答はさまざまな描写を通してある程度推察できるけれど、言葉で説明されるわけではありません。この読み取る楽しさがプリーストならでは。
そして、圧巻なのは舞台を夢幻諸島に移した第七部。さながらラテンアメリカ小説のように現実の同一性がずれを起こしていき、自分自身の出自すら変容していく。その酩酊感が素晴らしい。
最終章で描かれるのはあるひとつの美しい可能性だ。およそ信じ難いこの結末をしかし、しっかりと成立させるために(読者と、そして登場人物も)長い旅をしてきたのだなあ。
2017-11-24
Popeye - Deluxe Edition: Music From Motion Picture
1980年に制作された映画「Popeye」のニルソンによるサウンドトラック、その拡大盤2CD。Varese Sarabandeからのリイシューです。
まずディスク1はサントラ。ニルソンが書いた曲を出演俳優たちが歌ったもので、レコーディングは撮影と並行して、映画のロケ地であるマルタ島で行われました。ベーシックトラックの演奏はニルソンのほかレイ・クーパー、ダグ・ディラード、ヴァン・ダイク・パークス、クラウス・ファアマンらによるもので、あとから管弦がヴァン・ダイクのアレンジの元、L.A.で録音されました。
歌っているのがニルソンではないため、楽器の使い方からどうしたってヴァン・ダイクの作品という印象を受けます。独特のマジカルでドリーミーなオーケストレイション。特に、"Blow Me Down" という曲では'60年代後半のバーバンク・サウンドと共通する雰囲気がたまらない。ここでのロビン・ウィリアムズの歌声がちょっとボー・ブラメルズのサル・ヴァレンティノを思わせるんだな。また、"He's Large" のオケもまんまヴァン・ダイクのソロアルバムと変わらないような優美なもので、いいですね。
なお、今回のリリースでは元のサントラ盤には無かったスコアも収録されているのですが、それらにはニルソンやヴァン・ダイクは関わっていません。フルオーケストラによる重厚かつクラシカルなもので、録音はロンドン。映画のサウンドトラックという点では意義ある収録なのでしょうが、音の感触がまるっきり違うので個人的には混ぜないで分けて入れて欲しかった。
ディスク2はニルソンによるデモ集で、前半がL.A.のゴールド・スター・スタジオ、後半がマルタ島に移ってからの録音。シンプルながらファンからするとサントラよりこっちの方が馴染みやすいな、やっぱり。音質もばっちり。映画には使われなかった "Everybody's Got To Eat" もこれぞニルソンと思わされる麗しい出来であります。
また、女優のシェリー・デュヴァルに "He Needs Me" の歌い方を指導している様子も収録されており、これが実にインティミットでいい雰囲気。ところどころデュエットになっているのがまたいいですね。これはアルバム「Flash Harry」セッション中に行われていた模様。
そして、ボーナストラック扱いで "Everybody's Got To Eat" の映画用ヴァージョンと、あとはホームデモが3曲収録されております。ホームデモはピアノ弾き語りをポータブルのテレコで録ったような音ですが、諧謔味の薄い、素のニルソンが垣間見えるようではあります。
ブックレットのライナーノーツは関係者にインタビューした上で書かれた非常に詳細なもの。監督のロバート・アルトマンはニルソンについて、あいつはやめとけ、と皆から忠告されていたこと。そして案の定、ニルソンがプレッシャーからアルコールを手放せなくなり、なんとかヴァン・ダイク・パークスが仕事を進行させていたこと。劇伴のスコアもヴァン・ダイクが手掛ける予定であったが、ミュージシャンのストライキによって果たせなくなったことなどなど、読み応えは充分。
実のところ、このサントラ用のデモというのは昔からアンダーグラウンドでは出回っていて、その中には今回のリリースとはヴァージョンの違うものもあるのですが、さすがに切りがないか。
ともあれ、ニルソン、ヴァン・ダイク・パークスどちらのファンにとっても楽しめるリイシューだと思います。
2017-11-18
G・K・チェスタトン「ポンド氏の逆説」
チェスタトン晩年の短編集、その新訳版。英国で出版されたのは1936年、作者の死後だそう。
主人公のポンド氏は政府の役人であり、お馴染みのローマン・カトリックの神父や画家兼詩人などと比べるとそれほど変わったところがない、というか、あまり行動的ではないのだな。キャラクターとしては地味なほう。
各編の始めのほうで、会話中にポンドが逆説めいたこと――二人の男の意見が完全に一致したために、ひとりがもうひとりを殺すことになった、等――を口にすると、他の人物から意味がわからない、それはどういうことなのだ? と説明を求められる。それで、実はこういう話があってね、と過去に見聞きした事件について語り始める、といった具合。逆説が謎掛けになっているのですね。
そのポンドにつっこむ役割を果たすのが、友人のガヘガン大尉と政府の重要人物であるサー・ヒューバート・ウォットン。特にガヘガンにはブラウン神父譚におけるフランボウを思わせるところがある。犯罪者でも悪人でもないけれど、何度か事件に巻き込まれるうちにある種の改心をするに至る。
冒頭に置かれた「黙示録の三人の騎者」は暗い土手道を走る馬と、その周りに広がる原野のイメージが後を引き、本書の中でもっとも濃厚な印象を残す。そのトリックは時空を伸び縮みさせる文章と分かちがたく結びついていて、ミステリであることを忘れてしまいそうなぐらいだ。
他では、逆説そのものをミステリにした「博士の意見が一致する時」や、極めて抽象度の高い謎を平易な読み物として書き切った「名前を出せぬ男」はチェスタトンならではの作品で嬉しくなってくる。
また、殺人事件が起こるが真犯人探しがまるでなされない「ガヘガン大尉の犯罪」、まるっきり探偵小説のような事件の裏で進行していた意外な物語「恋人たちの指輪」、そして、ある古典中の古典をチェスタトン流に料理した「恐ろしき色男」などでは、ジャンルに対する自在なスタンスが楽しい。
情景描写は控えめで、ユーモアもわかり易く表現されているので、比較的軽めの読み物になっています。それでも、チェスタトンでしか書けなさそうな作品集でありますよ。
2017-11-12
The Replacements / For Sale: Live At Maxwell's 1986
リプレイスメンツ1986年のライヴ盤、二枚組でライノからのリリース。
近年、色んなミュージシャンの昔のライヴがあまり聞いたことのない会社から出ているのを見かけます。多くは放送用音源がソースであったりするのですが、このリプレイスメンツのライヴはそれらとは違い、元々が公式リリースを目的にレコーディングされたものであります。しばらくしてリードギターのボブ・スティントンがクビになったことで、当時はお蔵入りにされたのですね(ブートレグでは出回っていましたが)。
肝心の内容のほう、これが最高。
彼らのライヴには酔っ払ってやっているようなぐだぐだのものもあるのですが、ここでの演奏は気合いが入ったもの。この時期にはまだパンクバンドらしさを残していて、荒々しさも充分。曲によっては調子が外れているようなところも聴かれるものの、焦点が合った瞬間は実に格好いい。
また、分離のはっきりしたミックスがされていることで、二本のギターのアレンジがスタジオ録音より良くわかる。意外にパターンが豊富なのですね。ポール・ウェスターバーグも結構、印象に残るフレーズを弾いている。
しかし、若いですな。緩急も構成もなく、ひたすらタフでメロディのあるロックンロールが繰り出される。ライヴではお馴染みのレパートリーであったキッスやT・レックスのカバーも解釈や小細工なし。
ここでの "Can't Hardly Wait" を聴いてしまうと、翌年の「Pleased To Meet Me」収録ヴァージョンが物足りなくなってしまうかな。
2017-11-05
ジョン・ディクスン・カー「絞首台の謎」
1931年のアンリ・バンコランものであり、カーにとって長編二作目、その新訳です。
ロンドンのクラブに滞在するエジプト人は何者かに命を狙われていた。彼の元に犯行を予告するかのように絞首台のミニチュアが送られ、密室状態の机上には縊られた人形が出現。そして、ついに行方不明になってしまうのだが、その際には死体を運転席に乗せたリムジンがロンドン市街を暴走するのだから、いかにも扇情的。また、首切り役人を名乗る犯人が警察を挑発と、怪奇性がどぎついかたちで表現されています。
さらには古代エジプトの呪いまで盛り込もうとしているのだが、これはさすがに効果をあげていないか。
ロンドン中に立ち込める霧が印象的であり、これが時間や場所の感覚を曖昧にすることで謎の余地が生まれています。
バンコランはどうやら物語中盤で既に真相に到達してしまうようなのですが、この段階では不可能状況や犯人についてはっきりと語らず(当然ですが)、周辺の謎を解明するにとどまっているのが読んでいても煮え切らない。
そのかわり、ある登場人物が結構、あなどれない推理を披露してくれます。バンコランにばっさりと否定されてしまいますが、これは真相を知ってから振り返るとなかなか面白い。
その真相なのですが。あまり誤導が効いていないために犯人にはさほどの意外性はないか。また、事件を不可解に見せていた要素(もっとも、作中ではあまり強調されていませんが)についても、やや肩透かし。しかし、大量の伏線が回収される解決編は充分に読み応えがありました。
そして、絞首台が再度クロースアップしてくる結末は強烈です。
作家としてまだこなれていないせいか、ごたついてはいますが、まずまず面白く読めました。
2017-10-29
フィリップ・K・ディック「銀河の壺なおし〔新訳版〕」
西暦2046年、陶器の修復職人であるジョーは仕事にあぶれていた。既に陶器はプラスティックに取って変わられ、殆ど使われなくなっていたのだ。政府からの補助金で食いつなぎ、無為に過ごすことによる閉塞感に押しつぶされそうな毎日。しかし、そんなある日、ジョーの元にその技術を見込んだ巨額の仕事が舞い込んだ。
1969年の長編。
他の星系を舞台にした物語で、うだつのあがらない男の前に大きなチャンスが訪れる序盤はさながら冒険ファンタジー風。展開はスピーディで、なにやら過去がありそうなヒロイン、全てが書かれている預言書、光と闇の相克など、面白そうなアイディアが次々と登場して退屈するところはありません。
ユーモア要素も盛り込まれているし、異星生物の描写や、やたらに人間臭いロボットなども魅力的であります。
さくさくと読んでしまえるのですが、何しろ物語の様相が急激に変容していくので、さまざまなものが掘り下げられること無しに放置、という感は否めないです。半ばディストピア化した地球が全く省みられなくなっているのはなんとも。
にしても、この先読みの出来なさは凄いな。
読んでいる間は面白いのだけれど、何だかわかったようなわからないようなお話でした。まあ、気楽な娯楽作品として受け取ればいいのだろうな。
来月は『シミュラクラ』か。
2017-10-28
The Jam / 1977
ジャムの最初の2枚のアルバムを中心にしたボックスセット、4枚のCDにDVDという構成です。
これで彼らのアルバムは全てデラックス仕様でリイシューされたことになります。
| 判型はばらばらだが |
今回のリリースで不満を挙げるとすると、セカンドアルバムのデモが無いことか。いや、ディスク2に収められている「In The City」のためのデモの数々(うち半数はオフィシャル初登場)が実に聴き応えがあるのでね。バランスはいまいちだし奥行きには欠けるものの、生々しさや粗さが大いなる魅力となって迫ってくる。
またディスク4、始めのジョン・ピール・セッション8曲は「At The BBC」に入っていたのと同じ演奏ですが、ここでのギターの金属的な鳴りはまさにドクター・フィールグッド直系、という感じで嬉しくなってくる。個人的にはアルバム収録バージョンより好み。
その後に収められているのナッシュヴィルでのライヴは初登場のものだ。音質も悪くない。テンションの高さが空回りしているような曲もあるけれど、そこがこういった音源の楽しさでもある。
DVDのほうには珍しいものは無いようだ。1977年に絞ったことで分量も控えめ。だからこそ、一気に通して見てしまえる。何の演出もない、ただ演奏している姿を捉えているものだが、ただごとではない疾走感。当て振りのものでも全力だ。
結局のところ、ジャムのアルバムでは「In The City」が一番好みですね、個人的には。あっという間に過ぎていって、後には何も残さないような音楽。一方で、こういう表現は長く続けていくことができない、というのもまたわかる。
ポール・ウェラーは「In The City」について、収録曲の多くはザ・フーのファースト「My Generation」を下敷きにして書いたと語っているそうですが、"Non-Stop Dancing" なんかは同時期のエルヴィス・コステロと似たテイストがありますね。微妙にパブ・ロックっぽい。というか、スペンサー・デイヴィス・グループから来ているのかな。
2017-10-19
ジャック・カーリイ「キリング・ゲーム」
「ふたりとも殺してやる。グレゴリーは掃除用具を蹴飛ばし、便で汚れた水で手を濡らしたまま、暑くて悪臭の漂うガレージを歩きまわった。あいつらの目玉をくり抜く。腹を切り裂き、飢えたドブネズミを詰める……タマを木に釘づけしてから、頚動脈を剪定バサミで切る……」
二年に一度邦訳が出るカーソン・ライダー刑事シリーズ、これはその9作目で、米本国では2013年に出版された作品です。我が国では6作目と8作目がスキップされていまして、この作品ではそのうちの一つの殺人犯についても触れられているのですが、これは大丈夫なやつなのかしら。
ただ、出てくるのが毎度サイコパスのシリアルキラーなわけで、その辺りを考えると、うん、隔年でいいかな、という気がしないでもない。
今作では犯人が物語の最初から名前付きで登場している。そして、被害者たち個人の間には本当に関連がない。つまり、読者にとっては解くべき謎が存在しないし、次の被害者の予想も立てられないためサスペンスが生まれない。こうなってくるとなかなか、読み進めるのが大変。後半に入ると主人公の兄にしてサイコパスのエキスパート、ジェレミーも登場するけれど、役不足な感が否めない。この程度のことでジェレミーを呼ぶなよ、と思ってしまう。
犯人の自制にほころびが見え始めたときに、ようやく物語のエンジンが掛かってくる、そんな感じなのだ。
結末近くに至り、全てが明らかになったとき、それらの欠点は必然であったことがわかる。全てに意味があったのか、と。その意外性が発動するのが予想外の領域にあるため、かえってカタルシスに直結しないのは痛し痒し。
いわゆる伏線とは違う、クリスティ的な騙し絵の技巧が駆使された力作ではあります。ただ、ミステリとしての達成に感心はするけれど、エンターテイメントとして面白いかといわれると、どうかしら。
あと、シリーズはこの後からちょっと変わっていくようでありますね。
2017-10-18
The Rolling Stones / Aftermath (UK)
そしてこちらは英国での四枚目。
初めて全てをオリジナル曲で固めたアルバムで、質の高い曲が多い分、逆に落ちるものが目立ってしまっているかも。
US編集盤を取り上げたとき、このUK盤のほうがジャケットは渋くて格好いい、と書いた。けれど、1966年にしては古臭いという気もする。実際の音のほうはそれまでよりもカラフルだし、サイケデリックにつま先を踏み入れているようなものもある。"Think" あたりは次作「Between The Buttons」に混じっていてもおかしくない。
シングルでリリースされたのは "Mother's Little Helper" と "Lady Jane" のカップリング。どちらの曲にもそれほどの愛着はないけれど、改めて "Mother's Little Helper" を聴いてみると、骨格はもろキンクスですな。メロディはフォークっぽくって、ミドルエイトの展開からはビートルズの影響を感じます。うん、なんだか面白い。
このあたりから、ブライアン・ジョーンズがスタジオにあったさまざまな楽器を弄り回しはじめ、それはサウンド面における貢献といえるかもしれないけれど、それとともに二本のギターが絡みあうことが少なくなっていく。
とりあえずは、まだこの頃には一枚岩だった、そう思いたい。まとまりはないけれど、バンドとしての充実を感じるアルバム。
最近は "High And Dry" がストーンズ流カントリーブルースの原型、といった趣で気に入っております。
2017-10-14
The Rolling Stones / Aftermath (US)
1966年、米国での6枚目のアルバム、ですが。
実をいうと米盤仕様「Aftermath」は昨年のモノ・ボックスが出るまで聴いたことがなかったのだ。英国盤の曲順を勝手に変えて出していたものなわけで、ここにしか入っていない曲もない。ジャケットも英盤のほうが断然、渋くて格好いい。ボックスがなかったら聴くことはなかっただろう。
しかし実際に聴いてみると、それほどは悪くない。というか、元々の英盤が冗長なんですな。
英盤からの変更点としては、オープニングの "Mother's Little Helper" を "Paint It, Black" と差し換える、地味目な曲を3つ外す、A面最後の "Goin' Home" をアルバムの最後に廻す、というところですね。
まず、一曲目が変わるとアルバムとしての印象は大分、異なったものに感じられるのは確か。そして、"Paint It, Black" は特大ヒット曲であるけれど、一曲目向けでは無いという気もする。
次に、"Out Of Time" と "Take It Or Leave It"、そして "What To Do" の3曲が外されているのだが、さて。昔から思っていたけど英盤はB面がやや弱い。で、どれかを削るとなったとき、"Out Of Time" と "Take It Or Leave It" はどちらも良い曲なんだけれど、ポップ過ぎてアルバムの流れではちょっと浮いているかもしれない(僕ならどちらかを残して "It's Not Easy" を省くけれど)。で、"What To Do" はそもそもそんな大したものではない、満場一致だ。そんな風に納得してしまえ。
そして大作、"Goin' Home" の扱い。この曲でお腹いっぱいになって、もうB面は聴かなくていいや、そうなってしまったことが何度もありました。だから、最後にするという判断もありだな。
こんな感じで、全体をコンパクトにまとめながらバラエティも残した編集ではないでしょうか。あと、このサイズだとやはり " Mother's Little Helper " より "Paint It, Black" の方が必要になってくるのだな。
などと書いてきてなんなのだけど、オリジナルの米盤モノラルというのはステレオ・ミックスからのフォールド・ダウンらしいのだ(モノ・ボックス収録のほうは真正のモノラル・ミックスに差し換えられています)。だから、米盤「Aftermath」はステレオ・ミックスでないと本当に聴いたことにはならないのかも。いやあ、そこまでしては、もういいかな。
2017-10-07
Todd Rundgren / Hermit Of Mink Hollow
トッド・ラングレンが1978年にリリースした、ソロとしては8枚目にあたるアルバム。
全ての楽器をひとりで演奏、いわゆるワンマンレコーディングで制作されています。「Something/Anything?」(1972年)の4分の3もワンマンであったけれど、この「Hermit~」はミンク・ホロウという土地にある自宅スタジオにて、卓とブースの間を行ったり来たりしながら録音されたらしく、そのせいか、より密室性を強く感じさせるものになっています。
実はこのアルバムに関してはずっと、あまりピンと来ていなかったのだな。キラキラしたサウンドやシンセが、ユートピアならいいけどソロだと合ってないような気がして。また、音の分離が余り良くなく、ごちゃごちゃしている印象もありました。それが、最近になってなぜか無性に聴きたくなってきたのですが、いやあ、曲はいいのが多いのですね。
シングルとしてスマッシュヒットしたのが "Can We Still Be Friends"、これがやっぱり飛びぬけて良いすね。メロディの麗しさもさることながら、間奏部分のコーラスアレンジが浮遊感を湛えたサウンドとマッチしていて素晴らしい。それだけに深いエコー処理がなあ、もっと素で聴かせてくれよ、と思ってしまう。
このアルバム、アナログA面が「The Easy Side」、B面が「The Difficult Side」となっていますが、これはトッド本人ではなくレコード会社が決定した曲順だそう。
「The Easy Side」では先に触れた "Can We Still Be Friends" の他だと、スロウの "Hurting For You" が好みです。トッドのソウル路線、その典型ではありますが。
それから、"Too Far Gone" と "Onomatopoeia" はそれぞれボサノヴァとミュージックホール調のスタイルをトッドならではのアレンジで仕上げていて、独特の音楽になっていますな。
あと、"Determination" のベースラインがとてもビートルズ的で楽しい。この曲なんかを聴くと、ワンマンレコーディングでもしっかりとしたグルーヴは生み出せる、ということがわかります。
アルバム後半、「The Difficult Side」はやや地味な印象ですが、"Out Of Control" などのハードポップな要素はこの後のユートピアにおける方向につながっていくような感じも受けます。
2017-10-01
フィリップ・K・ディック「去年を待ちながら〔新訳版〕」
2055年、地球は星系間戦争に巻き込まれすっかり疲弊していた。敵対する異性人で巨大な昆虫のような外見をしたリーグ、彼らには地球との和平の意思もあるようなのだが、その一方で地球が協定を結んでいる勢力であり、地球人の遠い祖先でもあるリリスターはどちらかが破滅するまで戦争をやめるつもりはない。そして地球を監視し、そこからエネルギーを搾り上げ、あげくは支配下に置こうとしているのはリリスターのほうなのだ。
1966年長編、新訳が出たので再読。
いやあ、こんなに面白い話だったっけ? とにかく展開がスピーディで、だれ場がない。その分、アイディアが出しっぱなしで処理されてなかったり、理屈が通っていないところ、説明不足な部分もちらほらあるのだが、とにかくぐいぐいと進んでいく。
登場人物たちの多くは常に強いストレスを感じており、気の休まるときがない。じわじわと、しかし確実に地球は破滅へ向かっているようである。そんな中、ある場所で逃避のために持ち込まれた新種の幻覚性ドラッグ、JJ- 180。それは実は極秘裏に開発された戦争兵器であり、体内に入ると致死性のダメージを与えるものであった。一方で、副作用として一時的な時間旅行がもたらされるようなのだが。
物語後半には多元宇宙の存在が浮かび上がってくるのだけれど、設定そのものはかなりいい加減。しかし、そこから引き出される謀略小説的な展開がとてもスリリング。意外極まりない仮説が矢継ぎ早に打ち出され、ページを繰る手が止まらない。
それなのに、状況を救うために命がけで奔走したあげく、どうだっていいや、俺にはもっと大切なことがある、という個人的な事情に収束する結末。まったくもってディックらしい。
ハラハラ、わくわくさせて、そして何故か泣かせる。かなりとっちらかった作品です。
なお、ハヤカワ文庫ではこの作品に続いて『銀河の壺なおし』『シミュラクラ』『戦争が終わり、世界の終わりが始まった』、それぞれの新訳を4ヶ月連続で刊行とのこと。まあ何と言うか、歳を取っても読むものは変わらないのだなあ。
2017-09-23
The Delfonics / Tell Me This Is A Dream
デルフォニクスの(ベスト盤を除けば)四枚目のアルバム、1972年のリリース。
このアルバムまではプロデューサーとしてトム・ベルとフィリー・グルーヴのレーベル・オーナーであったスタン・ワトソンの二人が連名でクレジットされています。もっとも、トム・ベルはワトソンの強欲とリード・シンガー、ウィリアム・ハートの天狗ぶりに嫌気がさし、この時点で既に彼らとは袂を分かっていました。更に、トム・ベルによればワトソンはプロデュースどころか、スタジオで姿を見たことさえなかったそうであって、そうするとレコーディングの実態はメンバーのセルフ・プロデュースだったのか、あるいはアレンジャーのコールドウェル・マクミランが仕切ったのか、はたまたMFSBの誰かが何とかしたのか。
しかし、その重厚なサウンドはトム・ベルのような繊細さや個性はさすがに感じられないものの(シタールこそ残してありますが)、より濃密なスウィートさへ振り切っているようで、決して悪いものではありません。メンバー自身の手によるオリジナル曲も意外なほどいいのが揃っています。また、ボーカル面ではリードだけが突出することなく、よりグループらしいバランスの取れたものになっているかと。
収録されたどの曲も捨てるものが無いのですが、個人的には、新加入のノーマン・ハリスがアレンジを手掛けた二曲が特に好みであります。"I'm A Man" におけるドラマティックな展開、"Walk Right Up To The Sun" のオーソドックスなポップソングとしての出来、いずれも素晴らしい。
普段ソウルをあまり聴かないひとなら胸焼けするかもしれません。セールスがぱっとしなかったのも仕方ないか。
しかし、ヒット曲頼りではない分、一枚通してしっかりと作られている良いアルバムです。
2017-09-16
The Stylistics / The Stylistics (eponymous title)
ダスティ・スプリングフィールドの「A Brand New Me」を聴いたら、トム・ベルのアレンジってやっぱいいな、と感じ入って。色々と引っ張りだしていました。
トム・ベルが作編曲からプロデュースまで手掛けていたグループとして思いつくのは、大体の年代順にデルフォニクス、スタイリスティックス、そしてスピナーズといったところ。前二者はファルセット・リードのスウィート・ソウルというのが大雑把なイメージですが、スタイリスティックスの方が快活な抜けの良さを感じます。ラッセル・トンプキンズ・Jr.のクセの無いボーカル、そのキャラクターゆえ、ですかね。特にセカンド・アルバム以降は曲調のバラエティが広がり、メロウなミディアム・ダンサーでのテイストは同時期のスピナーズにも共通するものです。
といっても、スタイリスティックスに関しては今までデビュー・アルバム(1971年リリース)を一番多く聴いてきました。ヒット・シングルや有名曲が多いですしね(セカンドの「Round 2」は一曲目の "I'm Stone In Love With You" でつまずいてしまうのだな、ポピュラー味が強すぎるようで)。
全体に曲の質が高いアルバムだけれど、昔から "People Make the World Go Round" だけがどうにも、あまり好きではなかった。社会的メッセージのせいか、はたまたダークな雰囲気のせいか、どちらかといえばオージェイズ向きの曲じゃないかと。エンディングもやけに長いしね。
しかし、今回トム・ベルの仕事ということを意識して聴いていたせいか、バックトラックはいいじゃないか、と思いました。凄くバカラックっぽいのですね。この曲に限ったことではないけれど管楽器の柔らかな使い方がとても好みで、歌メロのラインをなぞるところなどたまらない。アール・ヤングのドラムもまた、格好いい。
しかし、手元にあるものでも聴き直せば発見があって、ますます新しいものに手を出す必要を感じなくなってきますな。
2017-09-12
レオ・ブルース「三人の名探偵のための事件」
「またしても密室殺人か」明らかにうんざりという様子だった「新機軸を期待したのだがねえ」
1936年に出版された、作者にとって探偵小説の分野におけるデビュー長編。
扱われているのはカントリーハウスにおける密室殺人です。はじめのうち物語はシリアスな雰囲気を保っているのだが、事件翌日になると呼ばれもしないのに名探偵と称される人物たち――勿体ぶった物腰の貴族、卵型の頭をした外国人、そして小柄な聖職者――が登場。更には、語り手も探偵小説内では当然であるような様式を意識するようになって、そこはかとないユーモアが醸され始めます。
物語の展開は尋問と捜査が続くむしろオーソドックスなもの。しかし、三人の名探偵たちのいかにも名探偵、という芝居がかったふるまいは、彼らのモデルとなっているであろう有名なキャラクターたちを想起させて実に楽しく、読み物として単調になることから救っています。
そして解決部分における推理合戦、ここが腰砕けだと単によくできたパロディ小説に収まってしまうところですが、それぞれの推理ががらりと違う上に密室トリックも複数、開陳されるのだから堪えられない。最後に明らかにされる真相はごくシンプルなもの、というのがまた洒落ている。
ジャンルの形式に意識的でありながら、あくまで娯楽性が優先されているのがいいじゃないですか。幕切れも気持ちよく、英国らしい楽しさが横溢した作品でありました。
2017-09-03
ヘレン・マクロイ「月明かりの男」
ドイツから亡命してきたユダヤ人である生化学者の死体、それをとりまく状況はあらゆる点から見て自殺を示していた。だが、故人は数時間前に、自分は決して自殺をするような人間ではない、と断言していた。さらに現場から走り去る怪しい人物がいたのだが、その目撃談はまさに三者三様で、およそ手掛かりにはなりそうになかった。
1940年発表、ベイジル・ウィリングものとしては二作目の長編。
事件の状況はディクスン・カーあたりが書きそうな種類のものだが、とりあえず捜査の焦点はそこには置かれない。こういった謎の扱い方はマクロイならではだな、と思う。しかし、夢遊病や嘘発見機など精神医学の要素と、戦争を有機的に埋め込んだプロットはなかなかに複雑なものであります。
ミステリとしてはとてもオーソドックスなつくりですが、物語が進行するにつれて被害者の生前の行動に非常に疑わしい点が浮かび上がってくるし、さらには新たな事件も起きて、と興味の途切れるところがありません。
書き振りの点でも、次はこいつが被害者になるのかな、と匂わせる呼吸など巧いものだ。また、後半に入って、読み慣れたひとなら疑うであろうが、全く検討されていなかった可能性が、ある人物によって指摘される。このタイミングも絶妙です。
謎解きには後年の作品ほど大量の伏線が盛り込まれているわけではありませんし、犯人が明らかになる瞬間もさらりとしたもの。しかし、心理学的な根拠ばかりで裁判で通用する物証はないだろう、と強がる犯人をベイジル・ウィリングが追い詰める過程は充分読み応えがありますし、ばら撒かれた偽の手掛かりこそが犯罪者を指し示す、というロジックは格好いい。
大きな驚きこそありませんが密度が濃く、フェアなフーダニットでありました。
創元推理文庫では来年「The Long Body」の刊行が予定されていて、これでベイジル・ウィリングものの長編はすべて訳出されることになる模様。あとは短編集のほうもお願いしたいところですが、ちょっと気が早いかな。
2017-08-27
The Rolling Stones / It's Only Rock 'n Roll
1974年、ミック・テイラーが最後に参加した作品。
なかなか印象がはっきりしないアルバムで。アナログではA面ばかり聴いていました。
オープナーである "If You Can't Rock Me" の迫力はただごとではない。つっかかっていくようなグルーヴが独特で、ライヴ演奏ではこれが再現できないようだ。間奏のチェンジ・オブ・ペース(キース・リチャーズによるベース・ソロが実にセンスいい)は決まっているし、エンディング部分におけるボーカルの入り方も最高。初めて聴いた高校生のときから今に至るまでずっとフェバリットの一曲だ。
テンプスのカバー "Ain't Too Proud To Beg" はこの時代に普通にモータウンのヒット曲を演ってしまう、というのがまたいいじゃないですか。初期のソウル曲カバーと違い、余裕が感じられ、なおかつしっかりとオリジナリティが感じられる仕上がり。この間奏も気が利いているよね。
で、タイトル曲である、"It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)"。ちょっとダルな雰囲気とサビでのテンションの対比が格好いい。これもライヴ演奏だと平坦に流れていってしまうのだな。アコースティック・ギターの使用が絶妙に効いていますが、ちょっといつもと違う乗りはドラムがケニー・ジョーンズだからかも。
続く "Till the Next Goodbye" はいかにも'70年代のアルバム曲、といったスロウ。ややカントリー入った雰囲気は、強烈な曲に挟まれると印象に残りにくいのは仕方がないか。
A面最後の"Time Waits For No One" はパーカッションも効果的な、ラテン色のあるスロウですが、やはりこの曲はミック・テイラーのソロですね。流麗でどこまでも伸びていくようなタッチが素晴らしい。
アナログB面にあたる後半は、ひとつひとつは悪くないけれど強力なものもないという感じ。なんだか落ち着いてしまっているのな。
アルバム最後の "Fingerprint File" はスライ&ザ・ファミリー・ストーンを下敷きにしたようなエレクトリック・ファンクで、良く動くベースはおそらくミック・テイラーによるもの。あまり、らしくないという気もして、この曲は好みが分かれるかも。テープスピードを上げているせいで、ボーカルもちょっとおかしな感じがする(DSDマスターの日本盤ではピッチが修正されています)。
やはり通して聴くとちょっと落ちてしまうな。3曲目までの勢いが凄いので捨て難いアルバムではありますが。
2017-08-17
コードウェイナー・スミス「三惑星の探求」
〈人類補完機構全短編〉、その三巻目にして完結編。前巻から一年以上かかりましたが、無事に出たので良かった。
最初の四作品はキャッシャー・オニールというキャラクターが登場する連作で、これらだけでペーパーバック化されていたもの。オニールは砂の惑星、ミッザーにおける元支配者の甥であったが、革命により追放の憂き目にあっていたという設定。
「宝石の惑星」 ミッザーの専制政権を打破するための物質的支援を求めるべく裕福な星、ポントッピダンを訪れたキャッシャー・オニールが、その地で起こっていた問題の解決を持ちかけられる。とても古典的なプロットだ。キャラクターからなにから典型的なスミス作品という感じ。
「嵐の惑星」 160ページ余りの中編で本書の中では一番ボリュームがある。すさまじい竜巻が吹き荒れる異世界が迫力を持って描かれる前半から、超常能力による戦い、そして人間性を復活させる物語へと展開。ひとつ、とても魅力的なアイディアがあるのだが、あえて膨らませることなく使われているのがもったいないような。濃厚なイメージが後を引く力作です。
「砂の惑星」 ミッザーへ戻ってきたキャッシャー・オニールは超人と化していた。やすやすと目的を果たしてしまったオニールは、次に聖なるものを求める旅を始める、というお話。宗教的な要素が強く、読んでいても正直あまりピンとこなかった。
「三人、約束の星へ」 この作品でのキャッシャー・オニールは脇役である。中心になる三人は宇宙船、各辺五十メートルの立方体、そして二百メートルある鋼鉄製の人間だ。彼らは遠い昔には普通の人間であり、今は人類に敵対する存在に対抗するために宇宙空間を飛び続けている。魅力的なキャラクターもさることながら、物語後半の急展開がなかなかに凄い。
これら四作品は作者が歳を重ねてから書かれたせいか、これより前の作品と比べると語りにおけるけれん味が控えめな感じを受けました。濃ゆい中身は紛れも無いコードウェイナー・スミスのものでありますが。
「太陽なき海に沈む」 コードウェイナー・スミスの奥さんであるジュヌヴィーヴが夫の死後に単独で書いた作品。読んでいてもあまり違和感がない、スミスの世界になっています。どこか中世の国を思わせるような惑星で繰り広げられる、醜悪な陰謀とそれを阻止しようとする物語だが、展開は少々あっけない。そして巨大猫のグリゼルダがかわいい。
あとは〈人類補完機構〉ものではない作品が六つ入っていて、すべて既読かな。
中では「西洋科学はすばらしい」の軽妙な語り、「達磨大師の横笛」や「アンガーヘルム」の放り出すような結末が印象に残るものでした。
2017-08-16
Dusty Springfield / A Brand New Me: The Complete Philadelphia Sessions
ダスティ・スプリングフィールドのフィラデルフィア録音集、米Real Gone Musicからリリース。ダスティ・ミーツ・ギャンブル&ハフであるこれらの曲、今回のリイシューでは全曲が新たに8トラックからミックスし直されたという点が大きいです。
収録曲のうち10曲目までがアルバム「A Brand New Me」(1970年)から。ただし、曲順はオリジナルとは全然違うものになっています。
リミックスの成果ですが、音質は非常に良くなっていますし、全体に曲のエンディングが長くなりました。その一方でバランスをいじったことでサウンドの質感が少し変わっています。ソウルっぽい臭みや、初期フィリーらしさは薄れたように思うし、迫力を増している分、繊細さも損なわれているのではないかしら。ボーカルがとても生々しく聴こえるようになり、ポップスとしてはより明快なものになったのですが、う~ん。オリジナル・ミックスとどちらが優れているか、という話ではないのだけれど、旧いライノ盤のCDも大事に置いておいたほうがいいか。
いずれにせよ、いい曲、いい歌唱揃いのアルバムではあります。
残り7曲はアルバムリリース後である'70年2月の録音で、殆どがボーナストラックなどのかたちでこれまで発表されてきたものですが、初登場の曲もひとつあります。
制作当時にはリリースされなかったこれらも、アルバム本編と比して見劣りするとは感じません。全てトム・ベルがアレンジを手掛けていて、通して聴いていて統一感があるのもいい。未発表であった "Sweet Charlie" は落ち着いた調子の曲ですが、これもしっかりと作られたものです。
ダスティ・スプリングフィールドは英本国においては(クレジットはされていないものの)共同プロデューサーとしてレコード制作をしていたのに、米国では出来上がってきたオケに歌を乗せるだけで、かなりストレスを感じていたそうだ。特に、アルバム「A Brand New Me」では選曲に関わることもなく(作曲はすべてケニー・ギャンブルが関わったもの)、曲を覚えてすぐに歌入れという仕事であったよう。しかし、考えようでは非常にプロフェッショナルなアルバム作りであったともいえるのではないかな、プロデュースは一切こちらにまかせときなさい、というのは。もう少しシンガーとしての自分に自信を持てていたら、米国での活動も違ったものになっていたかもしれないな、なんてことを思いました。
2017-08-06
Laura Nyro / A Little Magic, A Little Kindness: The Complete Mono Albums Collection
ローラ・ニーロの初期作品をモノラル・ミックスで収録した2CD、米Real Gone Musicからのリリース。マスタリングはヴィク・アネシーニが担当。
ディスク1に入っているのはヴァーヴからのデビュー・アルバム「More Than A New Discovery」(1967年)と "Stoney End" のシングル・ヴァージョン(アルバムとは歌詞が異なるもので、初CD化)。
この「More Than~」、これまでは「The First Songs」と改題して出し直されたステレオ盤がリイシューされていましたが、その「The First Songs」では曲順だけでなくミックスもオリジナル・ステレオとは異なっており、特に "Wedding Bell Blues" ではエコーがやたら深くかけられ、"Stoney End" においては音が歪んでしまっていました。
今まで、オリジナルの「More Than~」に使用されていたモノラルおよびステレオ・マスターはもう残っていないと思われていたのですが、入念にリサーチをやり直した末にモノラルのマスターテープが発見されたということです。
実際に聴いてみると、これはナチュラルな気持ちいい音。マスターがあまり使われていなかったからか、アネシーニによるマスタリングのおかげか、クリアでなおかつ聴き疲れしない。素晴らしい仕事です。
ディスク2はコロンビアに移ってからのアルバム「Eli And The Thirteenth Confession」(1968年)に、"Eli’s Comin’" のシングルエディットと "Save The Country" のシングル・ヴァージョン(「New York Tendaberry」のものとはまるっきり別アレンジ)を収録。
「Eli~」のモノラルはラジオプロモ向けに作成され、一般には出回らなかったもの。これもマスターテープをソースにしたということですが、ミックスそのものはステレオからのフォールド・ダウンなんですね。しかし、そう教えてもらわなければなかなか気付き難いだろうバランスのとれたミックスに(結果として)なっています。音質もいい。
きらびやかさならステレオ・ミックスのほうに分がありますが、このまとまりの感じられるサウンドも捨てがたい。ステレオ盤を聴いてやかましい女だな、と思ったひとにはこっちのがいいかも。
厚めのブックレットは非常に情報量が多いもの。新たにチャーリー・カレロやボーンズ・ハウにインタヴューしていて、とても読みでがあります。これによれば、Verveからのデビューに際してチャーリー・カレロも呼ばれてローラ・ニーロに会い、その歌も聴いていたのだが、カレロのスケジュールが開いていなかったのでそのときは共に仕事をするには至らなかったそうだ。それで、カレロと同様にフォー・シーズンズを手掛けていたハーブ・バーンスタインが担当することになったわけだと。
また、「Eli~」のリズムセクションとボーカルはスタジオライヴ形式で録音したが、ときにはボーカルの差し換えがあったとも認めています。
ともあれ聴いていて、惚れ直したというか、やっぱりいいな、と思いました。ポップソング、ソウル、ジャズが混じり合いながら、他の誰にも似ていない音楽。"Eli's Comin" のただ事ではない性急さはいつ聴いてもぞくぞくする。
まあ、「More Than A New Discovery」のモノラルだけでも充分に価値のあるリイシューじゃないすかね。
2017-07-31
青崎有吾「風ヶ丘五十円玉祭りの謎」
高校二年生の裏染天馬が活躍するミステリ短編集。
「もう一色選べる丼」 食堂の裏側に放置されていたほぼ食べ終わっている丼が乗ったトレイ。一体誰が、そして何故返却しなかったのか。
物証からのシャーロック・ホームズ風プロファイリングを基点にして、有り得た状況を推測していくというもの。設問のハードルが相当に高い分、推理には無理があるというか、そこまでの根拠はないだろう、という気はします。発想は面白いし、話の落としどころもとてもいいと思うのですが。
「風ヶ丘五十円玉祭りの謎」 神社で開かれている夏祭り、そこに出ている夜店の多くは何故かお釣りを百円玉ではなくて五十円玉で支払っていた。
脇になる謎は割と見当が付きやすい。その一方でメインとなる五十円玉のホワイは説明されてもあまりピンとこなかった。ロジックによる飛躍ではなくて、思いつきが飛躍しているように思える。あと、物語やキャラクターに対して無理やりに陰影を付けようとしているようで、収まりが悪く感じました。
「針宮理恵子のサードインパクト」 ブラバンの一年生はなぜ、練習場にしている教室から締め出されるのか。
やや小粒ながら、意外な気付きからの解決の流れには淀みがない。状況の反転も決まっていて、作品としてのまとまりもいい。アンソロジーとかに採られるのはこういうのだろうな。
「天使たちの残暑見舞い」 廊下から戸口を監視された状態で、教室内にいた二人の少女が消失。
盲点を突いた真相が見所なのかもしれないけれど、う~ん。こういう種類のアイディアならかちっとした謎解きとして構成するより、もっとあっさり処理したほうが良かったのでは。情景の意味が変化するところなどはセンスが光ります。
「その花瓶にご注意を」 廊下に飾られていた花瓶を割ったのは誰か?
裏染天馬の妹、鏡華が探偵役を務める、いわばスピンオフですが、ミステリとして手堅く作られています。犯人は早い段階で明らかになるものの、状況証拠しかないので当人は白を切り続ける。それをいかに追い詰めるか。証拠の出し方には例によって都合の良さを感じますが、演繹的な推理が予想外な場所へ導いていくという見せ方は好みです。
長編と同じようなロジックによるスリルを期待すると、ちょっと違いますね。意外性の配慮は嬉しいですし、気軽にさくさく読めるので、こういう行き方もありですか。
2017-07-30
The Beach Boys / 1967: Sunshine Tomorrow
1967年のビーチ・ボーイズにフォーカスした2CD。タイトルの「Sunshine Tomorrow」は "Let The Wind Blow" の歌詞にあるフレーズです。
ディスク1はアルバム「Wild Honey」を中心にしたもの。
〈Wild Honey Stereo〉は新たに作成されたステレオ・ミックス。このアルバムはあまり音数がないので、分離を良くしても仕方がないと思っていたのだけれど、楽器やコーラスのディテイルがなかなか新鮮で、何度も繰り返し聴いております。"I'd Love Just Once To See You" の抜けの良さが気持ちいい。一方で、音質の向上は期待していたほどではなかったです。奥行きに乏しい音像といい、元々の録音のせいなのだろうな。
続いては〈Wild Honey Sessions〉が14トラック。「previously unreleased」とあるものの、ボーカルが入ったトラックに関してはボックスセットやコンピレイションなどで小出しになっていたもののミックスや編集違いが殆どで、もう驚くようなものは残っていないのだとは思う。ただ、今では入手し難いものもあるので、こうやってひとところにまとめられたのはいいかと。一方で、バッキング・トラック・セッションでは初めて聴くものが多く、中でも "Darlin'" のそれは進行の過程が興味深い。また、未発表曲のものもありますが、断片的で喰い足りない。
〈Wild Honey Live 1967 - 1970〉は「Wild Honey」収録曲のライヴヴァージョンが5曲。録音バランスがあまり良くないのが残念。
最後は "Mama Says" のボーカルセッションの模様で、試行錯誤の様子が伝わってきます。
ディスク2の始めは(時系列でいくとこちらのほうが「Wild Honey」より先ですが)〈Smiley Smile Sessions〉より10トラック。成立過程からして、純粋にアルバム「Smiley Smile」のためのセッションというのは、量があまり無いのだろうな。それはともかく、「Smiley Smile」本編に漂う密室性というか、わけのわからない感じは薄いですね。リラックスしていて、けれど美しい音楽で、これは嬉しい驚き。
続いてはブートレグにもなっている未発表アルバム〈Lei'd In Hawaii "Live" Album〉の音源が14トラック。ライヴ盤制作のために録音されたハワイでのコンサートが充分なクオリティにないと判断され、スタジオでの演奏に歓声を被せた疑似ライヴ盤を作ろうとしていたのだけれど、結局は没になったという代物。それもさもありなん、恐ろしくゆっるゆるの演奏・歌唱であります。ボックス・トップス、マインドベンダーズのヒット曲や、ビートルズの "With A Little Help From My Friends" なども取り上げているのですが、そこにビーチ・ボーイズらしいセンスが付け加えられているとも感じられないなあ。
そして、〈Live In Hawaii, August 1967〉は実際にハワイで行われたライヴ録音から5曲。このときはブライアン・ウィルソンが鍵盤で参加していて、ブルース・ジョンストンが不在。ドライヴ感のないよれよれの演奏はリアルですね。曲としては "Gettin' Hungry" のライヴというのが珍しいか。
そして〈Thanksgiving Tour 1967〉は11月のライヴ演奏が3曲。このときにはサポートメンバーが追加されているせいか、ぐっと余裕のあるものになっています。
最後はスタジオ録音ふたつ。"Surf's Up" は「Wild Honey」期のセッションから。既出のものより前半部分が長くなっているのが嬉しいところ。そして、"Surfer Girl" は前出「Lei'd In Hawaii」での録音をアカペラにミックスしたものです。
玉石混交というか、統一感には乏しいセットではあります。'60年代におけるビーチ・ボーイズのライヴ演奏に興味がないひとには少々きついかもしれません。まあ、買う人はどっちみち買うんだろうけれど。
2017-07-20
Listen To Me: Soft Rock Nuggets Vol.4
ソフト・ロック・ナゲッツ、4枚目は英国産の音源を中心にしたもの。タイトルになっている "Listen To Me" はホリーズのあの曲です。ほかにもハーマンズ・ハーミッツの "No Milk Today" やトレメローズの "Silence Is Golden" などあって、ふうむ、弾が足りないのか? と思ってしまうのだが、それならアイルランドのフレッシュメンとか入れて欲しいな。なお、ブリティッシュ・ビート系でいくと、スウィンギング・ブルー・ジーンズの曲もあります。
一曲目に置かれているのはアイヴィー・リーグの "That's Why I'm Crying"。英国ポップにおいてファルセット・リードのコーラススタイルをいち早く打ち出したのが彼らではないでしょうか。そういったスピリットがみなぎっているように感じる曲です。
全体のざっくりした印象としては、米国ものと比べるとミドル・オブ・ザ・ロード寄りですね。サンシャイン・ポップじゃなくって、英国らしいくすんだ曇り空。トニー・マコウリィですから、と言ってしまえばそれまでだが、管弦の響きの違いが大きいかと。
初CD化のものはおそらく4曲、いいのが揃っています。ダニー・ストリートというひとの "Every Day" はトム・スプリングフィールドが手掛けた瀟洒なボサノヴァで、変化球ですがコンピレイション中ではいいスパイスになっています。しかし、クリス&ピーター・アレン(これは米国制作だと思うが)はそろそろアルバムごとリイシューしていただけないかしら。
この盤での個人的なベストはモンタナズの "You've Got Be Loved" になるかな。トニー・ハッチのセンスはやはり、当時の英国における制作方の中ではひとつ抜けているように思う。もっともハッチの場合、米国録音の可能性もあるのだが、あまりはっきりしたデータを見たことがないのだなあ。
2017-07-18
エラリー・クイーン「アメリカ銃の謎」
一年ぶりになる創元からのクイーン新訳で、1933年発表作。このシリーズは表紙デザインがいいですね。
二万人が詰め掛けた巨大競技場で、全観客が注視しているまさにその人物が射殺される。非常に派手な道具立てであります。
やったのは誰か、そして凶器はどこへ消えたのか。
前作『エジプト十字架の謎』では展開にスピード感があったのに対して、こちらは舞台のスケールを大きくしたせいか、なかなか捜査がはかどらない。また、終盤に入るまでエラリーが自分での考えを一切明らかにしないため、推理の興趣がいまひとつ盛り上がってこないのだ。ずっと捜査だけが続いているようで、作品の半ばくらいまでは単調に感じられるのが正直なところ。現場でかき集められた45挺の銃の検査のくだりなどは、もう少し省略を効かせてくれよと思う。
さらにいうと、特徴のあるキャラクターを何人も出しているけれど、物語の中で有機的に生かせていないのではないかな。
フーダニットとしてはさすがの切れであります。それまで一度も疑いをかけられなかった部分が表面化する際の衝撃といったら。手掛かりはあからさまな形で転がされているのだから、トリッキーな真相に対してリアリティを云々するのはそもそもフィクションとしてのレベルが違う話だ。
また、ある人物に対する調査が実は別の意図によるものだった、という誤導もシンプルではあるけれど気が利いています。
そして何気に異様なのは、作中である重大な役割を演じている人物に名前すら与えられていない、ということだろう。探偵小説、恐るべし。
次回刊行は『シャム双生児の謎』と思いきや、短編集『エラリー・クイーンの冒険』なのね。そいじゃ、また来年。
2017-07-15
It's A Happening World: Soft Rock Nuggets Vol.2
ワーナーのソフト・ロック・ナゲッツ、その続きです。
このコンピ、4枚のうち3枚目までは似たようなコンセプトのように思えます。まあ、当然ワーナー音源が多いわけなのですが、トミー・ジェイムズ&ザ・ションデルズ、アソシエイション、ハーパーズ・ビザール、ヴォーグズ、ディノ・ディシ&ビリーらの曲は3枚ともに収録されているし(ハーパーズ・ビザールは全部合わせて5曲にもなる)、カート・ベッチャーが関わった曲もそれぞれに何かしら入っています。
一方で、権利の関係かどうかはわかりませんが、A&Mから出ていたものではロジャー・ニコルズ&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズやサンドパイパーズが採られていますが、クリス・モンテズやクロディーン・ロンジェの曲は無いのですね。
それはともかく。2枚目、「It's A Happening World」でもよく知られている曲とともに、オブスキュアなシングル・オンリーのものをいくつも聴くことができます。ヴォーグズの "I've Got You On My Mind" も実は世界初CD化のよう。1968年のシングルB面曲で、後にホワイト・プレインズが取り上げたヴァージョンが知られているけれど、このヴォーグズ版のほうがいいかも。
この盤で、個人的に一番好きなのはオープナーであるブルース&テリーの "Don't Run Away" になりますね。ロニー&デイトナズの "Sandy" あたりと共通するインティミットな雰囲気と線の細いボーカルがマッチしていてたまらない。コーラスやハーモニーが導入部とエンディング、それとブリッジでしか使われていない分、対比が際立っているようにも感じます。
3枚目の「Birthday Morning」になるとレアなものがあまりなく、馴染みのある曲ばかり。おそらく今までCD化されていなかったのは、コングリケイションの "Sun Shines On My Street" 一曲だけではないかな。
その分、全体としての質は高い、とも言えるのだけれど。例えば、ロバート・ジョンなんてここに収められた "If You Don't Want My Love" さえあればいいと個人的には思っています。
しかし、ルビー&ザ・ロマンティクスはやはり "Hurting Each Other" かあ。良い曲ですけどね、他のも聴きたいんで、なんとかABCでの音源をまとめて欲しいものだ。
まあ、細かいことを言わなければ、単純に聴いて楽しいコンピレイションです。
2017-07-12
アガサ・クリスティー「マン島の黄金」
そもそもは1997年に出版された拾遺集で、一作を除いてそれまで単行本に収録されることの無かった短編が収められています。
それぞれの初出は1920~30年代とクリスティのキャリア初期であり、その内容はミステリとそうでないもの、両者の境界線上にあるものなど雑多なとりあわせです。
エルキュール・ポアロものがふたつ。「クリスマスの冒険」は後年に中編「クリスマス・プディングの冒険」へと書き直され、出来はそちらのほうがいいです。もう一方の「バクダッド大櫃の謎」は改作である「スペイン櫃の秘密」よりすっきりとしていて好みなのですが、この作品は『黄色いアイリス』にも入っているんだよなあ。
ハーリ・クィンものの「クィン氏のティー・セット」は1971年に複数の作家の短編を集めたアンソロジーに発表された作品で、雑誌掲載されていないのであれば、これがクリスティの生前、最後に発表された短編となるのだがどうだろう。作中でサタースウェイトはクィンと会うのが随分久しぶりということになっているけれど。
出来のほうは決して悪くないのですが、クィンものは一作だけを単品で読むとやや味わいが薄くなってしまうな。
タイトルになっている「マン島の黄金」は観光客誘致の宝探しイベントのために書かれた作品で、作中の登場人物とともに暗号を読み解いていけば、実際に隠された宝箱を見つけ出すことができる、という趣向だったそう。手は込んでいるものの純粋な読み物としては大したことはないかも。
クライムフィクションといえそうなのが「名演技」。恐喝者をいかにして追っ払うかについてのアイディアストーリーで、なんとなく成り行きの予想はついてしまうのですが、くっきりと浮かび上がってくる情景とその転換が実にうまい。
「崖っぷち」は健康な心がじわじわとゆがんで行く過程が読ませるサスペンス編で、実に良く書けているだけに陳腐なまとめがやや残念。
収録作品のうちミステリ要素のあるのはこのくらいですね。
「夢の家」は怪奇ファンタジーで、『死の猟犬』あたりのテイスト。話の持っていき方にも無理が目立たず、結構、堂に入った書きっぷりです。
「孤独な神さま」「炎の消えぬかぎり」「白木蓮の花」はロマンス小説。特に「白木蓮の花」は、ささいな謎が解けていくことで人間性が立ち昇る場面が非常に印象的。本書ではこれが一番気に入りました。
「壁の中」はミステリではないのだが、ある人物の知られざる内面がテーマといえるかもしれない。クリスティは人間性を描くのが真に迫っているわけではないけれど、そのプレゼンテーションのうまさによってキャラクターを印象づけるのだな。
「愛犬の死」は普通小説というか、ディケンズの線なんでしょうか。悲しいことはあるけれど、それでもあなたの人生は続いていくのよ、みたいな。ミステリ小説のとっかかりのエピソードだけを取り出して、書き込んだような作品だ。
残り物には福があったのかは微妙。純粋なミステリ的見地からすると残り物は、やはり残り物かと。当然にファン向きの一冊。
さて、七年余りをかけてクリスティのミステリ作品を読んできましたが、それも今回でおしまいです。ミステリ長編、作品集にまとめられた短編、オリジナルのプロットをもつ戯曲で入手可能なものはとりあえず読めたかな。
長かった。
2017-07-10
Silver And Sunshine: Soft Rock Nuggets Vol.1
我が国のワーナー編纂によるコンピレイション〈Soft Rock Nuggets〉、全4枚。
収録されている曲の半分くらいは既に盤で持っているので非常に悩んだのですが、世界初CD化のものが含まれているし、今回のはマスタリングがいいよ、という話もあって入手することにしました。
その1枚目、「Silver And Sunshine」と題されたものを聴いております。米国で1965~70年にリリースされたものが24曲収録。
アソシエイションやハーパーズ・ビザールなどのような定番ものとともに、今まで名前も聞いたことのないグループが入っていて、正直、あまり印象に残らない曲もありますね。
勿論、拾い物もあって。パット・シャノンの "Candy Apple, Cotton Candy" は、アル・キャプスの繊細かつドラマティックなアレンジが素晴らしいし、コロナドスの "Good Morning, New Day" は正統派のサンシャインポップという感じでこれも悪くないぞ。
この盤の最初の2曲が'65年のもの。そのうちゴールドブライアーズはドリーミーなアメリカン・ポップで、今聴くとやはり時代を感じます。この曲がオープナーでいいのかしら。
しかし、同じ年に出されたグレン・キャンベルの "Guess I'm Dumb"、ブライアン・ウィルソンが手掛けた曲でこれまでも色んな編集盤に採られていますが、これは本当、いつ聴いても新しい。ライナーノーツでVandaの佐野氏は「時代のはるか先を行っていたこの曲はグレン・キャンベルのファンには理解されず、残念ながらヒットしていない」と書いているのだけれど、この曲はコマーシャルとはいえないと思うのですね。だからこそ色褪せないのではないか、と。
一曲の時間が短いので通しでもストレスなく聴けるのが良いですね。このジャンルへのとっかかりにするとしたら、よろしいのではないかしら。
2017-07-02
Brenton Wood / The Very Best Of
"Gimme Little Sign" という曲が昔から好きで、ヒットソングとしてね、軽やかで。なんとなく盤として持っていたいなあと思って、ブレントン・ウッドのコンピレイションを購入しました。
これは今年になって出たCDで、Bicycle Musicというあまり聞いたことの無い会社からのもの。マスタリングは音圧高めなものの、非常にクリアな音ではあります。
ここに収められた曲は1967~70年くらいにDouble Shotというハリウッドの独立レーベルから出されたもので、各曲のプロデューサーとしてもそこのオーナーふたりがクレジットされています。
サウンドのほうはハリウッドと聞いて思い浮かべるものとは違いますな。もっとローカルな感じで、拡がりもそれほどはない。また、管弦が殆ど入っていなくて、主にオルガンが色付けとして使われているのが特徴。予算の問題だったのかもしれませんが、今聴くとその簡素さが個性になっています。特に'67年あたりの曲はオルガンがガレージパンクみたいなチープな響きをしているのが面白い。
ブレントン・ウッドというひとはソフトな歌い口が持ち味で、ときにファルセット混じりになるそれにはスモーキー・ロビンソンを思わせる瞬間もあります。作曲も自分で行っており、ややワンパターン気味ではあるものの、その節回しにはいやみがない。
"Baby You Got It" なんて曲はだいぶ後年のウィリアム・デヴォーンを思わせるようで、いいですな。
全体にソウルというより黒人ポップ歌手という感じ。このあっさりした音楽も悪くないすね。
登録:
投稿 (Atom)